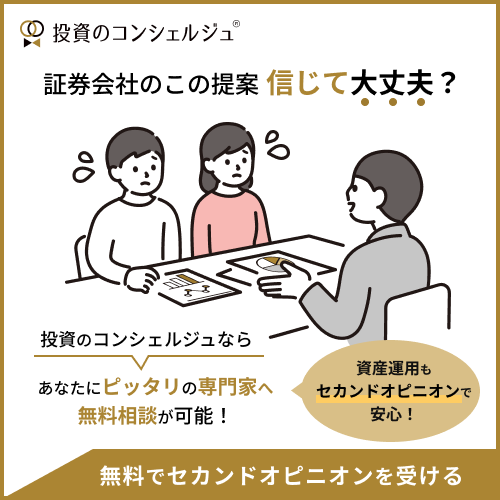学生納付特例を使った人のうち、追納しない人はどのくらいの割合いますか?
学生納付特例を使った人のうち、追納しない人はどのくらいの割合いますか?
回答受付中
0
2025/10/10 09:59
男性
30代
大学在学中に国民年金保険料の「学生納付特例制度」を利用したのですが、追納していない人も多いと聞きました。将来的に年金額が減る可能性があると分かっていても、実際に追納しない人がどのくらいいるのか、その割合や背景を知りたいです。経済的な事情だけでなく、どんな理由で追納をしない人が多いのかも教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
学生納付特例を利用した人のうち、10年以内に追納したのは約8.9%で、実に約9割の人が追納していません。厚生労働省のデータによると、追納率は一貫して低く、学生時代に猶予を受けた多くの人がそのまま未追納のままになっています。
追納が進まない主な理由は、まず制度の仕組みにあります。追納は承認月から10年以内しかできず、3年度目以降になると加算金が上乗せされるため、時間が経つほど割高になります。そのため、就職後に「いずれ払おう」と思っているうちに負担が増え、結果として追納しないまま期限を迎えるケースが多いのです。
また、20代前半は給与がまだ少なく、生活費や貯蓄を優先せざるを得ないため、まとまった追納資金を確保しにくい現実もあります。さらに、制度の理解不足や、手続きの手間が心理的なハードルになっている点も背景として挙げられます。
一方で、追納には明確なメリットがあります。学生納付特例や納付猶予による未納期間を1年分追納すると、老齢基礎年金が年額でおよそ2万円増えます。加えて、追納額は社会保険料控除の対象になるため、所得税や住民税が軽減されるという税制上の利点もあります。
資金に余裕がある場合は、早めに部分的でも追納を始めるのが望ましいです。加算金を抑えられるうえ、10年を超えると追納自体ができなくなるため、時間との勝負になります。もし期限を過ぎてしまっても、60歳以降の任意加入や厚生年金で働き続けることで年金額を増やす方法もあります。
全体として、追納しない人が多数派である現状は、経済的・制度的・心理的な要因が重なった結果です。ただし、追納の効果は大きく、老後資金の安定につながります。家計の状況を見ながら、無理のない範囲で早めの対応を考えることが、将来の安心に直結します。
関連記事
関連する専門用語
学生納付特例制度
学生納付特例制度とは、20歳以上の学生が国民年金の保険料を納めることが経済的に難しい場合に、申請することで在学中の保険料納付が猶予される制度です。この制度を利用すると、納付していない期間も年金の受給資格期間としてカウントされるため、将来の年金受給に不利にならず、卒業後に収入を得てから追納することも可能です。 対象となるのは、大学・大学院・短大・専門学校・高等専門学校などに在学している学生で、一定の所得以下であることが条件です。資産運用やライフプランの面では、学生時代から年金制度に関わる意識を持ち、将来の備えとして制度のしくみを理解しておくことが大切です。
追納
追納とは、過去に国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間について、後からさかのぼって保険料を納めることをいいます。この制度を利用することで、将来受け取る老齢基礎年金の受給額を増やすことができ、年金の受給資格期間にも有利に働きます。 ただし、追納できるのは原則として免除・猶予を受けた期間に限られ、単なる未納期間には適用されません。また、追納には期限があり、原則として免除・猶予された年度の翌年度から起算して10年以内となっています。 追納することで本来の保険料負担に戻る形になりますが、2年以上前の期間については加算金が上乗せされることがあります。経済的に余裕があるときに計画的に追納を行うことで、将来の年金額をしっかり確保することができます。
加算金
加算金とは、金融商品や保険商品などで、通常の利息や配当などに上乗せされる追加的な金銭のことを指します。主に定期預金や債券、保険契約などで、一定の条件を満たした場合に支払われることがあります。例えば、特定の期間まで解約しなかった場合や、特定のキャンペーン中に契約をした場合などに、通常より高い利率が適用されることがあります。投資家にとっては、利回りを高めるための一つの要素となりますが、加算金が適用される条件をよく確認しないと、思ったよりも受け取れないケースもあるため注意が必要です。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
社会保険料控除
社会保険料控除とは、健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険などの社会保険料を支払った場合に、その金額を所得から差し引くことができる所得控除の一種です。これは、納税者の生活を守る公的制度に協力しているという前提で、税負担を軽くするための仕組みです。 本人が支払った分だけでなく、配偶者や親族の保険料を本人が負担している場合にも控除の対象になります。会社員であれば給与から自動的に天引きされた社会保険料も対象となっており、年末調整や確定申告の際に自動的に反映されるケースが多いです。税額を計算する際の重要な調整要素となるため、税制の基本知識として知っておくと役立ちます。
任意加入
任意加入とは、法律や制度によって義務づけられているわけではなく、自分の意思で加入することを選べる仕組みのことを指します。資産運用の分野では、主に年金制度や保険商品などで使われる用語です。たとえば、国民年金の任意加入制度では、定年退職後も年金を増やしたい人や、年金受給資格期間を満たしていない人が自ら希望して加入できます。また、投資信託や確定拠出年金(iDeCo)のように、自分の将来の資産形成を目的として自発的に加入する場合も任意加入と呼ばれます。強制ではないため、自分のライフプランやリスク許容度に応じて判断することが大切です。