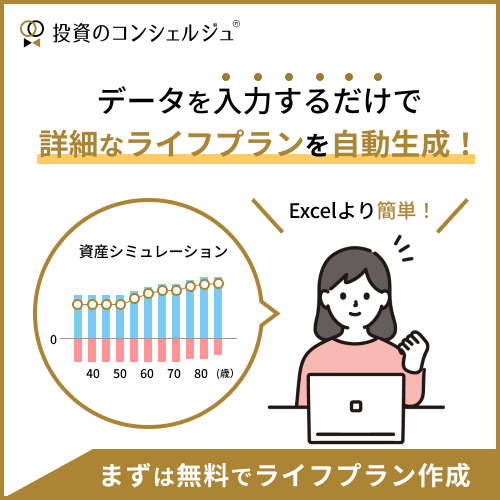「年金だけでは暮らせない」とよく聞きますが、これは本当にすべての高齢者に当てはまるのでしょうか?
「年金だけでは暮らせない」とよく聞きますが、これは本当にすべての高齢者に当てはまるのでしょうか?
回答受付中
0
2025/10/10 09:59
男性
60代
老後の生活費について、最近「年金だけでは暮らせない」とよく耳にしますが、それがどの程度現実的なのか気になります。すべての高齢者が年金だけでは生活できないのでしょうか。平均的な年金受給額と、実際にかかる生活費の差についても知りたいです。また、現役世代のうちからどのくらいの資産形成をしておくべきなのか、具体的な目安があれば教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
「年金だけでは暮らせない」という言葉は、すべての高齢者に当てはまるわけではありません。持ち家か賃貸か、厚生年金か国民年金中心か、地域の物価、医療や介護の状況、生活水準、就労の有無などによって結果は大きく異なります。
ただし、平均的なデータを見ると、年金だけでは月に数万円の赤字になる家庭が多く、貯蓄の取り崩しや資産運用、就労、支出の見直しが必要になるケースが一般的です。
具体的に見ると、標準的な夫婦世帯の年金額は月23万円前後で、一方で高齢夫婦世帯の平均支出は月約28万円といわれています。つまり、平均的には毎月約3万~5万円の不足が生じており、単身世帯でも約2〜3万円の赤字です。
これはあくまで平均値であり、持ち家や地方在住の方であれば十分暮らせる場合もありますが、賃貸や都市部在住の方では不足が大きくなる傾向があります。
老後に「年金だけで足りる」人の特徴としては、長期間厚生年金に加入していたこと、持ち家で住宅費が少ないこと、支出を年金額に合わせて抑えられること、または一部でも働き続けて収入を得ていることが挙げられます。
一方で「足りない」人は、国民年金中心で加入期間が短い、賃貸住まいで家賃負担が重い、都市部で生活費が高い、または医療・介護費の負担が大きいといった背景があります。
今から備えるには、まず自分の「年金見込額」と「老後の生活費」を数値で把握することが大切です。まず「ねんきんネット」で将来の受給額を確認し、不足分を明確にすることが第一歩です。
その上で、受給開始を繰り下げて年金額を増やす、NISAやiDeCoで長期的に資産を育てる、住居コストを見直す、医療・介護費に備えて公的制度や民間保険を組み合わせるなど、できることから対策を進めましょう。
関連記事
関連する専門用語
生活費
生活費とは、日常生活を送るために継続的に必要となる支出の総称です。具体的には、食費・住居費・光熱費・通信費・交通費・保険料・日用品費などが含まれます。ライフプランニングにおいては、将来の資金計画を立てる上で最も基本となる項目です。 生活費は、家計の固定費と変動費に分けて整理するのが一般的です。固定費には家賃や住宅ローン、保険料、通信費など毎月一定額がかかる支出が含まれ、変動費には食費や交際費、レジャー費など月によって増減する支出が該当します。この分類によって、支出の見直しや節約余地の把握が容易になります。 ライフプランニングの観点では、生活費を「現役期」「リタイア後」に分けて見積もることが重要です。現役期は収入に応じた支出バランスの最適化が課題となり、リタイア後は年金や金融資産からの取り崩しを前提に、生活水準を維持できる金額を算出します。特に老後資金のシミュレーションでは、「生活費=必要生活費+ゆとり費」という考え方が用いられ、前者は最低限の生活維持費、後者は旅行や趣味などの豊かさを加えた支出とされます。 また、生活費はインフレ率や家族構成の変化、ライフイベント(子どもの教育、住宅購入、介護など)によって大きく変動します。したがって、定期的に見直しを行い、支出の現状と将来見通しを可視化することが、安定したライフプラン設計の第一歩となります。
厚生年金
厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。
国民年金
国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入しなければならない、公的な年金制度です。自営業の人や学生、専業主婦(夫)などが主に対象となり、将来の老後の生活を支える「老齢基礎年金」だけでなく、障害を負ったときの「障害基礎年金」や、死亡した際の遺族のための「遺族基礎年金」なども含まれています。毎月一定の保険料を支払うことで、将来必要となる生活の土台を作る仕組みであり、日本の年金制度の基本となる重要な制度です。
ねんきんネット
ねんきんネットとは、日本年金機構が提供しているオンラインサービスで、自分の年金に関する情報をインターネット上で確認できる仕組みです。年金の加入履歴や将来の年金受取見込み額、保険料の納付状況などを、自宅のパソコンやスマートフォンからいつでも確認できます。 ログインには基礎年金番号やマイナンバーが必要で、安全性にも配慮されています。紙の通知だけではわかりにくかった年金情報を自分で管理できるようになるため、資産運用や老後の生活設計を考えるうえで非常に便利なツールです。
NISA
NISAとは、「少額投資非課税制度(Nippon Individual Saving Account)」の略称で、日本に住む個人が一定額までの投資について、配当金や売却益などにかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託などで得られる利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を使えばその税金がかからず、効率的に資産形成を行うことができます。2024年からは新しいNISA制度が始まり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを併用できる仕組みとなり、非課税期間も無期限化されました。年間の投資枠や口座の開設先は決められており、原則として1人1口座しか持てません。NISAは投資初心者にも利用しやすい制度として広く普及しており、長期的な資産形成を支援する国の税制優遇措置のひとつです。
iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を作るための私的年金制度です。20歳以上65歳未満の人が加入でき、掛け金は65歳まで拠出可能。60歳まで原則引き出せません。 加入者は毎月の掛け金を決めて積み立て、選んだ金融商品で長期運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。加入には金融機関選択、口座開設、申込書類提出などの手続きが必要です。 投資信託や定期預金、生命保険などの金融商品で運用し、税制優遇を受けられます。積立時は掛金が全額所得控除の対象となり、運用時は運用益が非課税、受取時も一定額が非課税になるなどのメリットがあります。 一方で、証券口座と異なり各種手数料がかかること、途中引き出しが原則できない、というデメリットもあります。