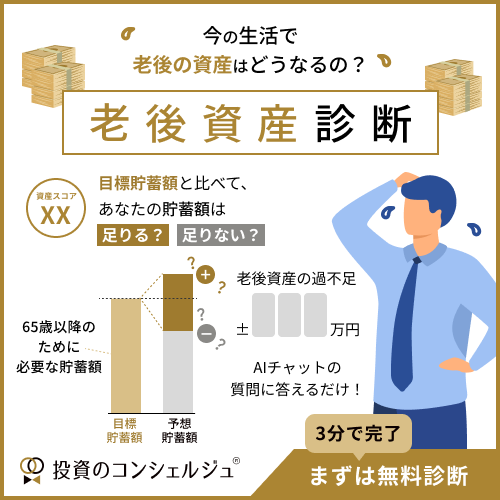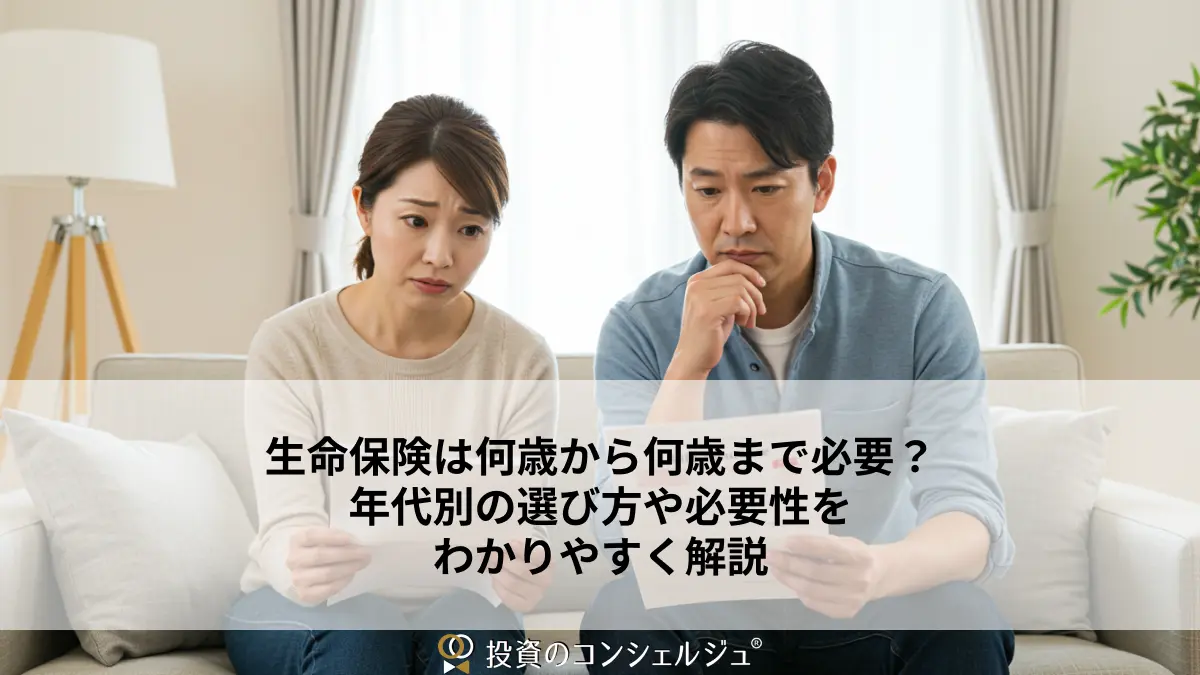60歳で定年後再雇用に切り替わりました。保険の見直しをするとき、必要な保障の考え方を教えてください。
60歳で定年後再雇用に切り替わりました。保険の見直しをするとき、必要な保障の考え方を教えてください。
回答受付中
0
2025/10/17 09:12
男性
50代
60歳で定年後再雇用となり、収入や生活スタイルが変わりました。現在加入している生命保険や医療保険は現役時代のままですが、このタイミングで見直すべきでしょうか。現在、子どもは独立しており、配偶者と二人暮らしです。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
60歳で定年後再雇用となったこのタイミングは、保険を見直す絶好の機会です。結論から申し上げますと、「大きな死亡保障の削減と、医療・介護費は貯蓄で対応する」が基本方針となります。お子様が独立され、収入も現役時代の6割程度になった今、現役時代と同じ保険内容を維持する必要はありません。
まず必要保障額の考え方が大きく変わります。現役時代に必要だった「遺族の生活費保障」や「教育資金の確保」といった大きな死亡保障は、もはや必要性が大幅に低下しています。
現在考えるべき保障は、配偶者の当面の生活資金として300万〜500万円程度の死亡保障、そしてご自身の老後資金の確保です。医療や介護のリスクについては、貯蓄で対応する方が合理的な選択となります。
大幅に削減できるのが死亡保障です。現役時代に2,000万〜3,000万円といった高額な死亡保障に加入されている場合、終身保険は葬儀費用や相続対策として300万〜500万円程度に縮小し、定期保険はお子様が独立済みなら解約も検討対象となります。遺族年金や貯蓄を考慮すると、過剰な死亡保障は保険料の無駄遣いになります。
医療保険やがん保険については、すでに加入されているものは保険料負担が許容範囲であれば継続しても構いませんが、新規で契約する必要はありません。60歳以降の新規加入は保険料が非常に高く、保険料として支払う総額と受け取れる可能性のある給付金を比較すると、割に合わないケースが多いためです。
日本の公的医療保険制度には高額療養費制度があり、月額の医療費負担には上限が設けられています。たとえば70歳未満で年収約370万〜770万円の方であれば、月額の自己負担上限は約9万円です。入院が長期化しても、貯蓄から対応できる範囲に収まります。
介護費用についても同様です。公的介護保険により、実際の自己負担は原則1割(所得に応じて2〜3割)となります。仮に月額20万円の介護サービスを利用しても、自己負担は2万〜6万円程度です。これも貯蓄から十分に対応可能な金額です。民間の介護保険は保険料が高額なわりに給付条件が厳しいため、その保険料を貯蓄に回す方が賢明です。
過剰な保障は削減し、削減した保険料分を貯蓄や資産運用に回すことで、より柔軟な資金活用が可能になります。医療費や介護費は、いつ、どの程度必要になるか予測できないため、保険で固定的に備えるより、貯蓄として自由に使える形で持っておく方が合理的です。
関連記事
関連する専門用語
必要保障額
必要保障額とは、万一の際に残された家族が現在と同等の生活水準を維持しながら、将来の教育費や住宅費といった支出も含めて安心して暮らしていけるよう、生命保険などで準備すべき金額を指します。具体的には、遺族の生活費、子どもの教育資金、住宅ローンの残債、葬儀費用などの「必要資金」から、公的遺族年金、勤務先の死亡退職金、既存の貯蓄や保険などの「準備済み資金」を差し引くことで算出します。 この必要保障額は、家族構成や年齢、子どもの進学予定、住宅ローンの残り期間など、個々のライフプランによって大きく異なります。たとえば、子どもが小さいうちは教育費や生活費の負担が長期にわたるため保障額は大きくなりがちですが、成長とともに必要な保障額は徐々に減少していきます。また、配偶者の就労状況や資産形成の進捗によっても必要な金額は変動します。 そのため、保険を一度加入したら終わりではなく、ライフステージの変化に応じて定期的に見直すことが重要です。保障が過剰であれば保険料の無駄払いになり、逆に不足していればいざというときに家族が困ることになります。こうしたリスクを避けるためにも、保険はライフプラン全体の中での位置づけとして考えることが不可欠です。 保険加入を検討する際には、営業担当者の提案を鵜呑みにせず、自分の生活設計に照らして必要な保障内容を見極めることが大切です。保障の目的や期間、公的制度とのバランス、そして家計や資産運用との整合性を踏まえた設計にすることで、無理なく持続可能な保険の活用が実現できます。必要に応じて、ライフプランニングに精通した中立的な専門家に相談し、現状の見直しと将来設計を行うのも有効な方法です。
終身保険
終身保険とは、被保険者が亡くなるまで一生涯にわたって保障が続く生命保険のことです。契約が有効である限り、いつ亡くなっても保険金が支払われる点が大きな特徴です。また、長く契約を続けることで、解約した際に戻ってくるお金である「解約返戻金」も一定程度蓄積されるため、保障と同時に資産形成の手段としても利用されます。 保険料は一定期間で払い終えるものや、生涯支払い続けるものなど、契約によってさまざまです。遺族への経済的保障を目的に契約されることが多く、老後の資金準備や相続対策としても活用されます。途中で解約すると、払い込んだ金額よりも少ない返戻金しか戻らないこともあるため、長期の視点で加入することが前提となる保険です。
定期保険
定期保険とは、あらかじめ決められた一定の期間だけ保障が受けられる生命保険のことです。たとえば10年や20年といった契約期間のあいだに万が一のことがあれば、保険金が支払われますが、その期間を過ぎると保障はなくなります。保障期間が限定されているため、保険料は比較的安く設定されています。特に子育て世代や住宅ローンを抱えている方など、特定の期間だけ万が一の保障を重視したい場合に適しています。貯蓄性はなく、純粋に「保障のための保険」である点が特徴です。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。
介護保険制度
要介護状態になった高齢者やその家族の負担を社会全体で支えるために設けられた公的保険です。40歳以上の国民が加入者となり、保険料を納めることで、要介護認定を受けた際に訪問介護やデイサービス、施設入所など多様な介護サービスを自己負担1割〜3割の範囲で利用できます。 給付内容や利用者負担割合は、所得区分や要介護度によって異なるほか、市区町村が主体となって保険料率や地域のサービス体制を決定しているため、住んでいる自治体ごとに細かな違いがある点も特徴です。必要な介護を適切に受けながら、家計への影響を抑えるためには、要介護認定の申請やケアマネジャーによるケアプラン作成など、制度の手続きを理解し、早めに相談することが大切です。
遺族年金
遺族年金とは、家計の支え手である人が亡くなった際に、残された家族の生活を保障するために支給される年金のことです。公的年金制度の中に組み込まれており、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。対象となるのは、主に配偶者や子どもで、支給額や期間は家族構成や被保険者の加入状況などによって異なります。遺族年金は、残された家族が安定した生活を続けるための公的な支援制度として、生活設計においてとても重要な役割を果たします。