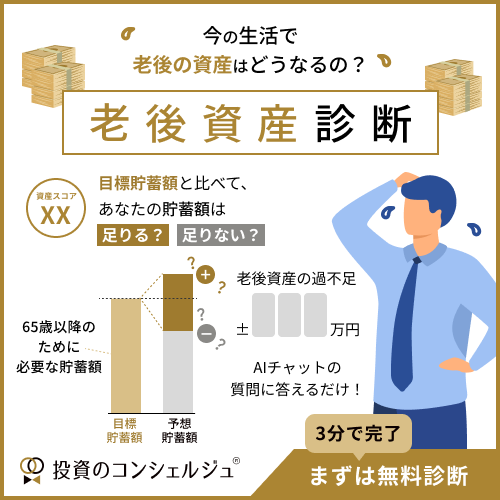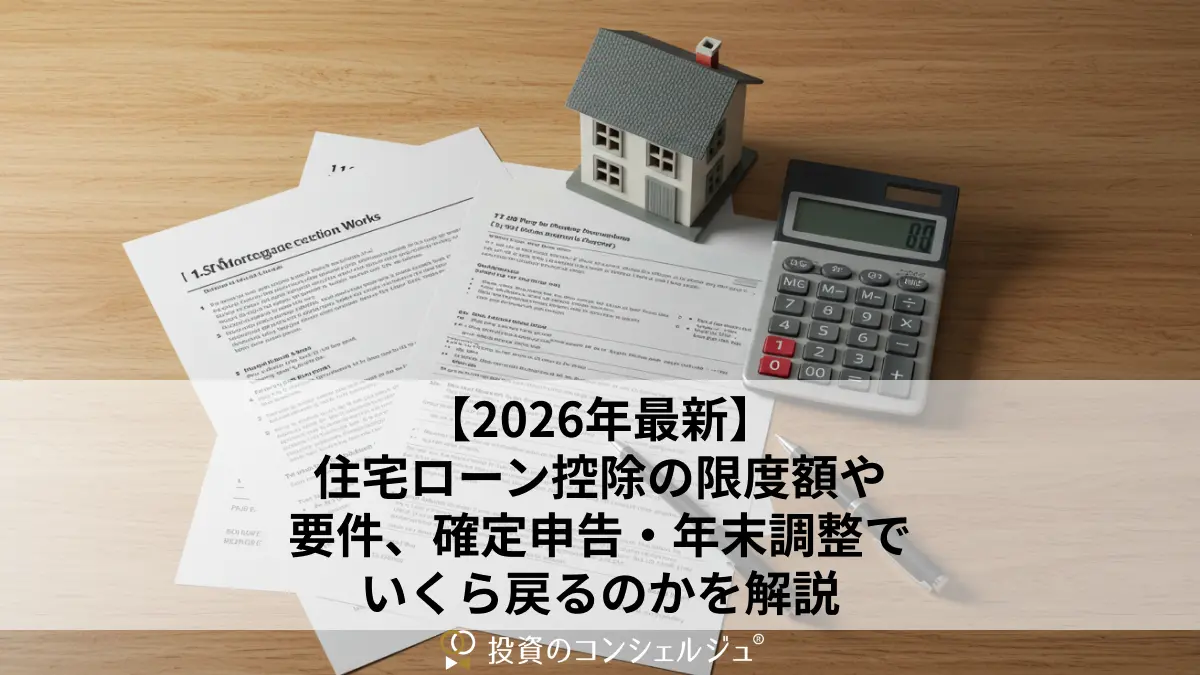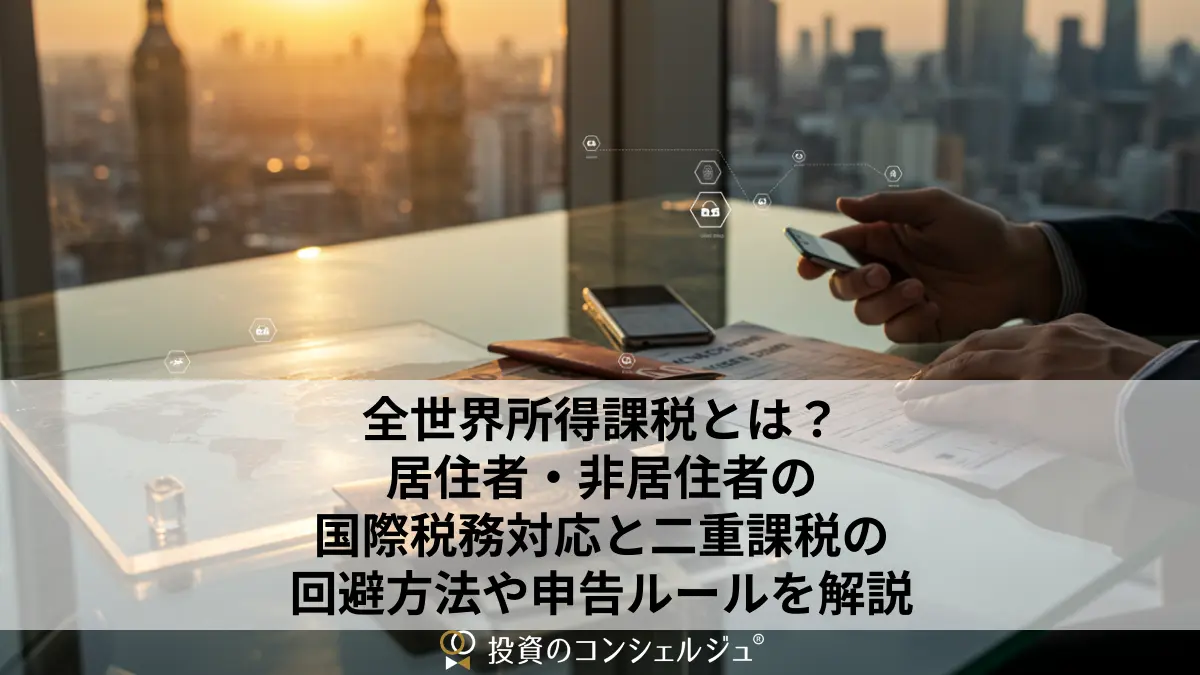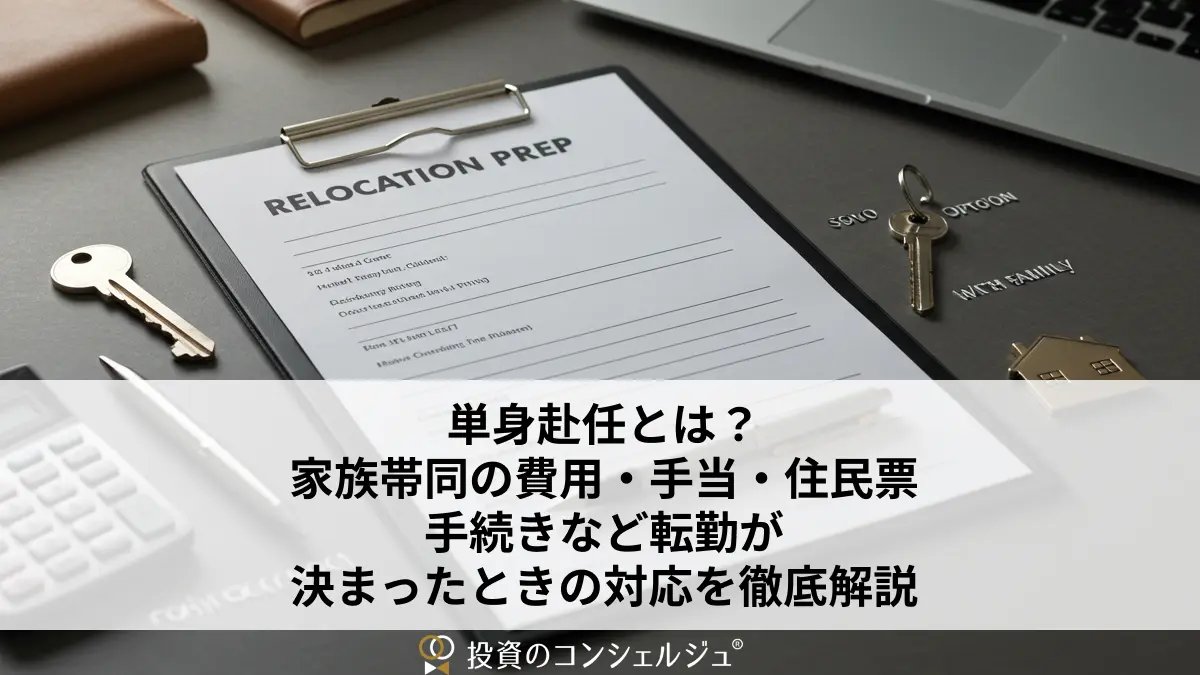投資の知恵袋
Questions
検索結果0件
テーマを選択(複数選択可)
単身赴任する場合でも住宅ローン控除は受けられますか?
回答受付中
0
2025/09/29 09:07
男性
30代
単身赴任で家族と離れて生活する場合でも、住宅ローン控除を受け続けられるのか気になっています。転勤期間が長期に及ぶ場合や、住民票の移動が必要になるケースなど、税務上の取り扱いがどのように判断されるのかを専門的に教えていただきたいです。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
結論から言うと、単身赴任をしていても家族がマイホームに住み続け、帰任後に自分も戻ることが見込まれる場合は、住宅ローン控除を継続して受けることができます。判断の基準となるのは年末時点の居住状況であり、住宅取得時に定められた入居要件を満たしているかどうかが重要です。
具体的には、家族が住宅を取得から6か月以内に入居し、年末まで継続して住んでいれば、単身赴任中でも居住しているものとみなされます。海外赴任の場合も、2016年4月1日以降に取得した住宅であれば、家族が居住を続けており、その年に日本の国内源泉所得があれば適用可能です。2016年3月31日以前に取得した住宅の場合は、非居住期間は対象外ですが、帰国後に残りの期間について控除を再開できます。
一方で、家族も帯同して自宅が空き家になる場合や賃貸に出す場合は、その年は適用されません。ただし、帰任して再び住むようになれば残りの期間について控除を再適用できます。この場合、控除期間が延びることはなく、中断分は失われます。
手続きとして、単身赴任で家族が住み続ける場合は特別な申請は不要で、通常どおり年末調整や確定申告を行えば足ります。ただし、辞令や光熱費の記録など、実際に居住していることを示す証拠は保管しておくと安心です。家族帯同などで控除を中断する場合は、転勤命令による不在を税務署に届け出ておき、帰任後の確定申告で必要書類を添えて再適用の手続きを行います。
住宅ローン控除は、取得から6か月以内の入居、床面積の要件、10年以上の返済期間、所得制限などの基本条件を常に満たしている必要があります。2024年以降の新築については、省エネ基準を満たすことが要件に追加されている点にも注意が必要です。
つまり、単身赴任であっても家族が居住を続けている限り控除は守られますが、家族が離れたり住宅を貸したりすれば一時中断となり、帰任後に残り期間だけ再開される仕組みです。自分の取得時期、家族の居住状況、所得の有無を確認したうえで、必要に応じて税務署への届出や証拠資料の保管を行うことが大切です。
関連ガイド
関連質問
2025.09.29
男性
“単身赴任で、住民票を移さないとどうなりますか?”
A. 単身赴任先が生活の本拠なら住民票は移すのが原則です。家族が自宅に住み続ける場合は移さなくても違法ではありませんが、税金や手続き上の影響に注意が必要です。
2025.09.05
男性30代
“ペアローンの場合住宅ローン控除はどのように適用されますか?”
A. ペアローンは夫婦それぞれに住宅ローン控除が適用され、合計で大きな節税効果を得られますが、返済リスクには注意が必要です。
2025.09.05
女性30代
“住宅ローン控除は中古マンションの購入でも使えますか?”
A. 中古マンションでも築年数や耐震基準などの条件を満たせば住宅ローン控除を利用可能です。購入前に必ず条件を確認しましょう。
2025.09.29
男性40代
“単身赴任の場合確定申告をすると特定支出控除で税金が安くなると聞きましたが、どういう仕組ですか?”
A. 単身赴任で自己負担した帰宅旅費や転居費などが給与所得控除額の2分の1を超えると、その超過分を特定支出控除として申告でき税金が軽減されます。
2025.06.07
男性40代
“単身海外赴任者の居住者判定と税務対応はどうすべきですか?”
A. 家族が日本に残ると居住者扱いになりやすく、海外給与も日本で課税対象です。赴任前に判定基準・出国税・控除可否を確認しましょう。
関連する専門用語
住宅ローン控除(住宅ローン減税/住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用して自宅を購入・新築・増改築した際に、一定の条件を満たせば年末時点のローン残高に応じた金額が所得税から控除される制度です。住宅取得を支援する目的で設けられており、最大で13年間にわたり税負担を軽減できます。 控除額は原則として「年末のローン残高×0.7%」を基準に算出され、各住宅区分ごとに定められた借入限度額までが対象となります。控除しきれなかった分は翌年度の住民税からも一定額控除されます。 適用を受けるにはいくつかの条件があります。主な要件は、①自ら居住すること、②取得から6か月以内に入居し年末まで継続居住すること、③床面積が50㎡以上(一定要件を満たせば40㎡以上も可)、④返済期間が10年以上のローンであること、⑤合計所得が2,000万円以下であること、などです。親族間の売買や勤務先からの無利子・超低利ローンは対象外となります。 また、新築住宅は省エネ基準の適合が必須条件とされており、長期優良住宅やZEH水準の住宅は借入限度額が優遇されます。中古住宅では新耐震基準に適合していることが必要で、古い住宅では耐震証明書の提出が求められるケースもあります。増改築やリフォームも一定の工事要件を満たせば対象になります。 手続きは初年度に確定申告が必要で、会社員の場合は2年目以降は年末調整で対応できます。必要書類として、住宅ローンの年末残高証明書、売買契約書や登記事項証明書、省エネ性能に関する証明書などが挙げられます。 住宅ローン控除は、住宅購入時の資金計画や税負担に大きく影響する重要な制度です。適用条件や期限を正しく理解し、事前に必要書類や証明の取得を進めておくことが安心につながります。
年末調整
年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が1年間に納めるべき所得税の額を、年末に雇用主が計算し直して精算する手続きのことです。通常、毎月の給与からあらかじめ見込みで所得税が源泉徴収されていますが、年末に実際の収入や各種控除(配偶者控除、扶養控除、保険料控除など)を反映させて正確な税額を算出し、過不足を調整します。 税金を払いすぎていた場合には還付され、足りなかった場合は追加で徴収されることがあります。年末調整によって、多くの給与所得者は確定申告をしなくても納税が完結する仕組みになっており、手間の軽減と課税の公平性を両立させる重要な制度です。ただし、自営業者や副業収入がある人、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい人などは、年末調整だけでは対応できず、別途確定申告が必要になります。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。
国内源泉所得
国内源泉所得とは、所得税法上、日本国内で生じたとみなされる所得のことを指します。たとえば、日本国内で得た給与、事業所得、不動産の賃貸収入、利子、配当、著作権料などが該当します。非居住者にとっては、日本国内で得たこの国内源泉所得のみが課税対象となるのが原則です。一方で、居住者は全世界所得(国外も含むすべての所得)が課税対象となります。 どの所得が「国内に源泉がある」と判断されるかは、所得の種類ごとに所得税法で細かく定義されています。たとえば、日本企業から受け取る配当や、日本にある不動産からの賃料は、非居住者であっても日本で課税される「国内源泉所得」に該当します。この区分は、国際的な税務判断や租税条約の適用可否にも大きく影響する重要な概念です。
非居住者
非居住者とは、所得税法第2条第1項第5号に基づき、「国内に住所を有さず、かつ1年以上引き続いて居所を有しない個人」を指します。一般には、海外に生活の拠点を移して1年以上継続して滞在している方、特に海外赴任や永住を前提とした移住者などが該当します。 非居住者になると、日本の税制や金融制度上の取扱いが大きく変わります。税務上、日本は非居住者に対して「国内源泉所得」のみ課税権を持ちます。たとえば、日本国内勤務に対応する給与や賞与は国内源泉所得とされ、15.315%の税率で源泉徴収されます。非居住者は住民税や累進課税の対象外であるため、金額にかかわらずこの定率で課税が完結し、原則として確定申告も不要です。 この仕組みを活用すれば、高額報酬を受け取る場合でも、居住者の最大55%課税に比べて大幅に税負担を抑えられる可能性があります。ただし、非居住者として認められるには、住民票の除票だけでなく、生活拠点・勤務実態・業務の指示系統などから総合的に実態が判断されます。租税回避とみなされないよう、恒久的施設(PE)課税や居住国側での課税リスクにも留意が必要です。 一方、海外勤務に対応する給与・賞与は国外源泉所得とされ、日本では非課税です。報酬の支払元や雇用契約の内容によっては判断が分かれるため、租税条約の有無や適用範囲の確認も重要です。 退職金については、従業員の場合は国内勤務に対応する部分が、役員の場合は全額が国内源泉所得とみなされ、20.42%で源泉徴収されます。なお、退職所得の選択課税制度を使えば、居住者と同様に退職所得控除や1/2課税が適用され、還付を受けられることがあります。 金融面では、非居住者になることで日本の銀行口座や証券口座に制限がかかることがあります。多くの銀行では非居住者の口座維持に制限があり、住民票を除票後に届け出を行っていないと口座凍結のリスクもあります。証券口座の特定口座も廃止され、一般口座への移管が必要になります。 NISA口座も非居住者になると原則利用できなくなります。ただし、会社都合による海外赴任で「非課税口座継続適用届出書」を提出すれば、最長5年間は非課税枠を維持可能です。この場合でも、新規買付や積立は停止され、自己都合による移住では口座の廃止が必要です。 また、日本と非居住者の居住国との間に租税条約がある場合、課税が軽減または免除されるケースもあります。たとえば、台湾との間では、国外勤務に対応する退職手当の一部が日本で非課税となる取り扱いがあります。 このように、非居住者となることで税制・金融制度の適用が大きく変わります。とくに高額所得者や国際的な勤務を行う方にとっては、非居住者ステータスの活用が節税につながる一方で、税務リスクや手続き上の注意点も少なくありません。実態に基づいた制度設計と事前の準備が不可欠です。
関連質問
2025.09.29
男性
“単身赴任で、住民票を移さないとどうなりますか?”
A. 単身赴任先が生活の本拠なら住民票は移すのが原則です。家族が自宅に住み続ける場合は移さなくても違法ではありませんが、税金や手続き上の影響に注意が必要です。
2025.09.05
男性30代
“ペアローンの場合住宅ローン控除はどのように適用されますか?”
A. ペアローンは夫婦それぞれに住宅ローン控除が適用され、合計で大きな節税効果を得られますが、返済リスクには注意が必要です。
2025.09.05
女性30代
“住宅ローン控除は中古マンションの購入でも使えますか?”
A. 中古マンションでも築年数や耐震基準などの条件を満たせば住宅ローン控除を利用可能です。購入前に必ず条件を確認しましょう。