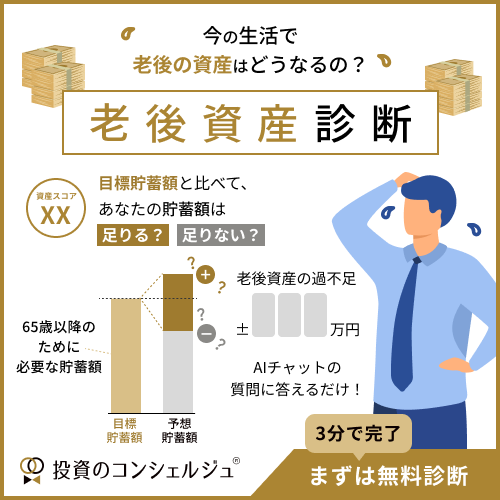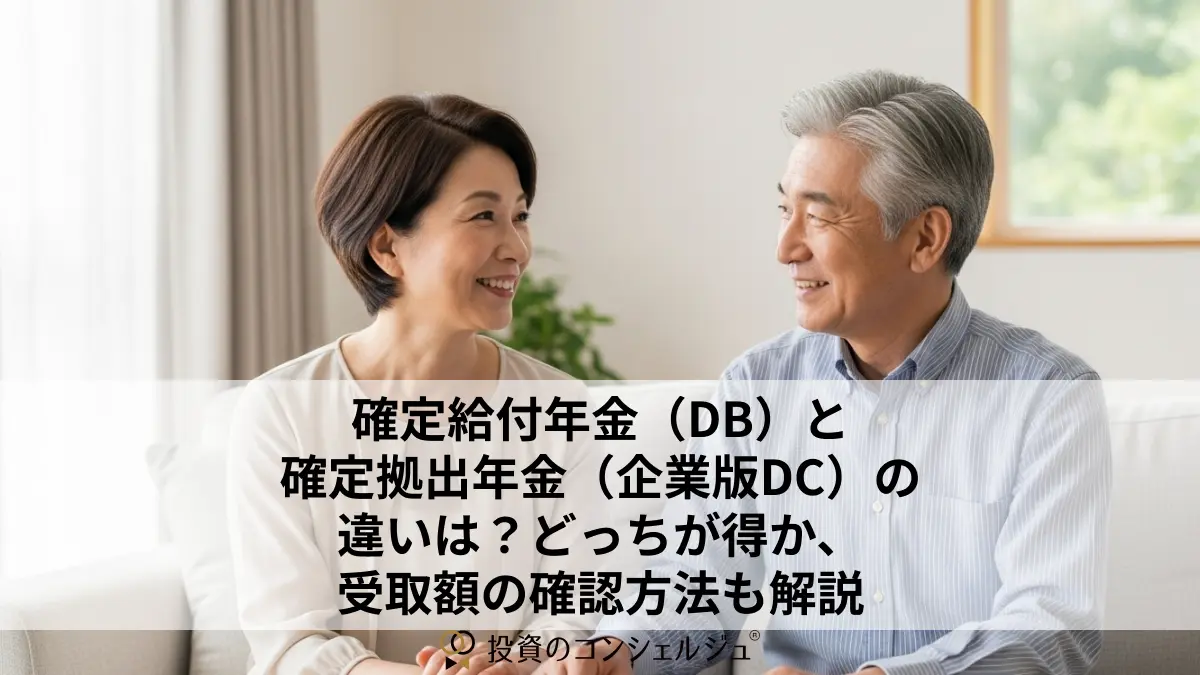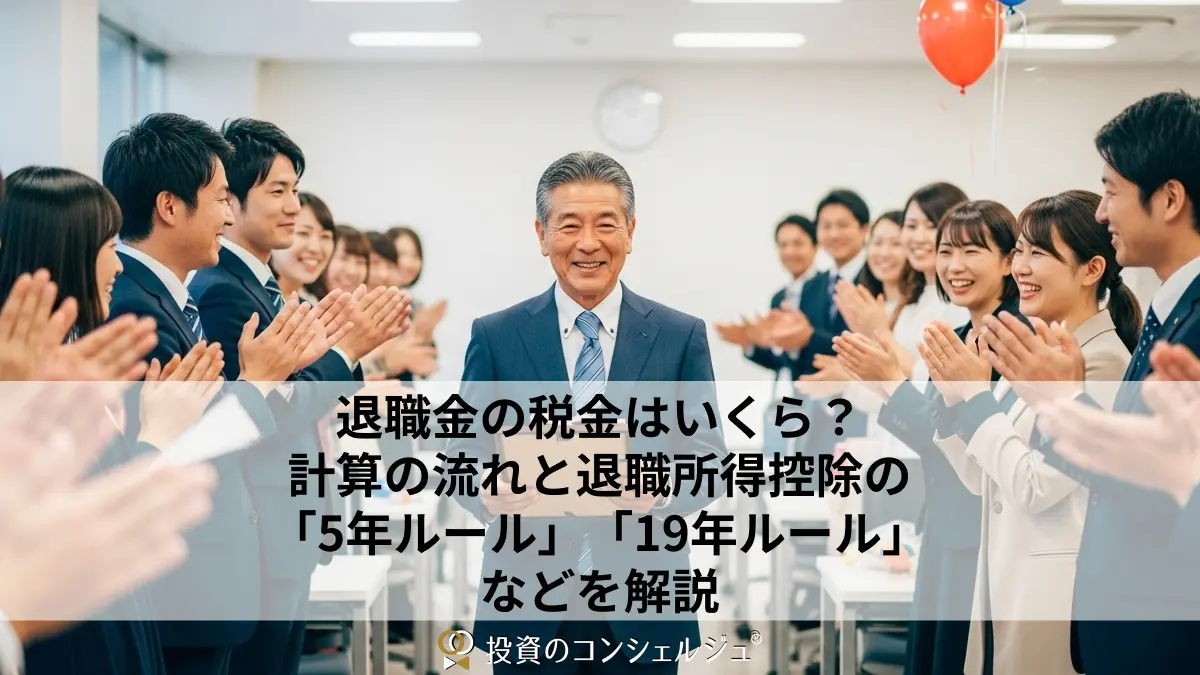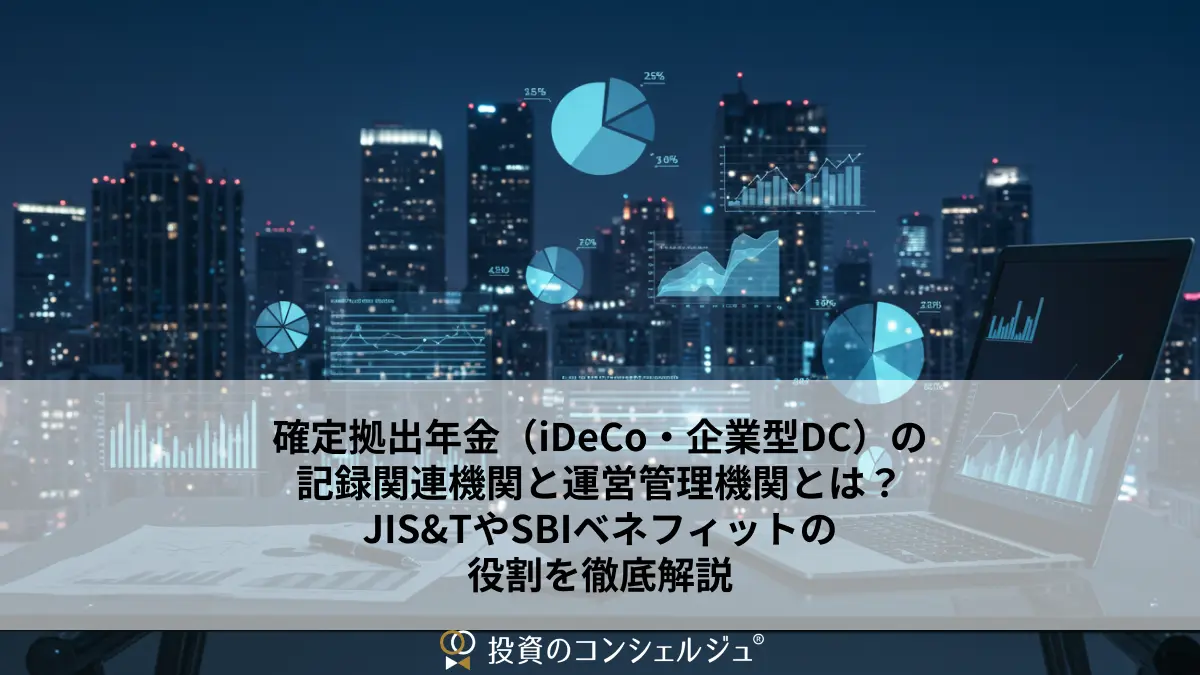企業年金はいつまで受け取れますか?
企業年金はいつまで受け取れますか?
回答受付中
0
2025/10/15 09:13
男性
60代
企業年金の受取期間は終身なのか有期なのか、制度や企業ごとに違いがあると聞きました。確定給付(DB)や確定拠出(DC)で、受け取り開始年齢・期間(5年や10年、有期・終身)、途中変更の可否などを教えてください。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
企業年金をいつまで受け取れるかは、制度の種類と会社の規約によって異なります。確定給付型(DB)は終身年金か有期年金(5年・10年など)を選べることが多く、終身を選べば一生、有期を選べば指定した期間で受給が終了します。
DBの一般的な例では、65歳から開始する終身年金または10年間の有期年金を選べます。終身に「保証期間」を付けることもでき、受取開始後すぐに亡くなっても一定期間は遺族に支給されますが、その分月額は少し下がります。開始年齢は多くの企業で60~65歳が中心で、繰上げや繰下げも可能です。
確定拠出型(DC)は「一時金」か「分割受取」を選び、分割年数は商品や規約で決まります。退職時に選択した方法で、支給が一生続くか一定期間で終わるかが決まります。
DCでは60歳以降に受給を開始でき、一括受取の場合はその時点で完了します。年金方式を選ぶと、5~20年などの期間で分割受取が可能で、運用残高が尽きれば支給も終了します。受給方式や期間は開始前なら変更できる場合もありますが、開始後は基本的に変更できません。
受取期間や開始年齢を最終的に決めるのは、退職時や受給手続き時です。在職中に支給期間が確定することはなく、在職中に受け取りを開始できるかどうかも制度によります。
税制上、年金形式で受け取る場合は雑所得として公的年金等控除の対象となり、一時金で受け取る場合は退職所得として退職所得控除が適用されます。長期勤続ほど税負担が軽くなります。税金や社会保険料の兼ね合い、受取後のライフスタイルなどを考えて、受取方法を選択しましょう。
受取前には会社の年金規約やDCのパンフレットを確認し、①受給開始年齢、②受取方式、③有期の年数、④保証期間の有無、⑤開始後の変更可否、⑥在職中開始の可否、⑦税制上の扱いを確認しておくことが大切です。企業年金の受け取り方は老後の資金計画に直結するため、公的年金や個人年金、金融資産とのバランスを踏まえて選ぶことが重要です。
関連記事
関連質問
2024.07.24
男性60代
“退職金とiDeCoの一時金での受け取りが退職所得控除に与える影響について教えて下さい”
A. 退職金とiDeCoを同時期に一時金受取すると控除が減ります。先にiDeCo、5年以上後に退職金を受け取ると手取りを最大化できます。
2025.10.09
男性60代
“退職金はどのように受け取るのが一般的ですか?手続きや受け取り方法を知りたいです。”
A. 退職金の受け取りは「一時金」「年金」「併用」の3種類。税制優遇のある一時金か、定期収入を得られる年金かで負担が変わります。確定拠出年金との受取時期も重要で、最適な方法は個人の状況により異なります。
2024.08.08
男性
“企業DCは個人にとって節税にならないので、iDeCoの方がいいのでしょうか”
A. 会社負担の企業型DCは社会保険料も減り節税効果が大きい。まずDC上限まで拠出し、不足分をiDeCoまたはマッチング拠出で補うのが合理的。
2025.07.04
男性60代
“公的年金の繰上げ・繰下げ申請の手続きは、どのようにすればよいですか?”
A. 65歳は年金請求書を提出すれば、受給が始まります。繰上げは60歳以降に自分で繰上げ請求書を年金事務所へ提出、繰下げは65歳時の請求書を出さず待機し、希望時に繰下げ請求書を出せば増額受給が始まります。
2025.07.04
男性60代
“年金繰上げ・繰下げの「損益分岐点」を教えてください。”
A. 損益分岐点は、繰上げなら受給開始から20年10か月、繰下げなら10年11か月経過時点です。これ以降に長生きすると、選択肢が不利・有利に逆転します。
関連する専門用語
確定給付企業年金 (DB)
確定給付型企業年金(DB)とは、企業が従業員の退職後に受け取る年金額を保証する企業年金制度です。あらかじめ決められた給付額が支払われるため、従業員にとっては将来の見通しが立てやすいのが特徴です。DBには規約型と基金型の2種類があります。規約型は、企業が生命保険会社や信託銀行などの受託機関と契約し、受託機関が年金資産の管理や給付を行う仕組みです。基金型は、企業が企業年金基金を設立し、その基金が資産を運用し、従業員に年金を給付する仕組みです。確定拠出年金(DC)との大きな違いは、DBでは企業が運用リスクを負担する点であり、運用成績にかかわらず従業員は決まった額の年金を受け取ることができます。一方、DCでは従業員自身が運用を行い、将来受け取る年金額は運用成績によって変動します。DBのメリットとして、従業員は退職後の給付額が確定しているため安心感があることが挙げられます。また、企業にとっては従業員の定着率向上につながる点も利点となります。しかし、企業側には年金資産の運用成績が悪化した場合に追加の負担が発生するリスクがあるため、財務的な影響を考慮する必要があります。
確定拠出年金(DC)
確定拠出年金(DC)は、毎月いくら掛金を拠出するかをあらかじめ決め、その掛金を自分で運用して増やし、将来の受取額が運用成績によって変わる年金制度です。会社が導入する企業型と、自分で加入する個人型(iDeCo)の二つがあり、掛金は所得控除の対象になるため節税効果があります。 運用対象は投資信託や定期預金などから選べ、運用益も非課税で再投資される仕組みです。60歳以降に年金や一時金として受け取れますが、途中で自由に引き出せない点に注意が必要です。老後資金を自ら準備し、運用の成果を自分の年金額として受け取る「自助努力型」の代表的な制度となっています。
終身年金
終身年金とは、一度受給が始まると、契約者が生きている限り年金が支給され続けるタイプの年金です。主に民間の年金保険や国民年金基金、企業年金などで採用される形式で、老後の長生きリスクに備えるための仕組みとして重視されています。たとえば、90歳まで生きた場合でも、支給は一生涯続くため、資金が尽きる心配が少なくなります。支給額は契約時に決められており、途中で変更されることは通常ありません。 資産運用の視点からは、定期的な安定収入を確保する手段として終身年金は非常に有効であり、特に退職後の生活費の柱として設計する際に重宝されます。ただし、早期に亡くなった場合は支払った保険料よりも受け取る年金総額が少なくなることもあるため、遺族保障とのバランスも検討が必要です。
有期年金
有期年金とは、あらかじめ決められた一定の期間(たとえば10年や20年など)にわたり、定期的に年金として一定額の給付金が支払われる年金のことです。この期間が満了すれば、たとえ被保険者がその後も生存していても給付は終了します。一方で、受給者が途中で死亡した場合でも、残りの期間分は遺族などに支払われる仕組みがある「確定年金型」の商品も多く存在します。 有期年金は、老後資金や教育資金、住宅ローン返済など、あらかじめ使い道や必要な期間が想定できる資金設計に適しており、一定の計画性を持った資産運用の手段として活用されます。終身年金と異なり、長生きリスクをカバーするものではないため、ライフプランに応じた併用が重要です。
退職所得控除
退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。
公的年金等控除
公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。
関連質問
2024.07.24
男性60代
“退職金とiDeCoの一時金での受け取りが退職所得控除に与える影響について教えて下さい”
A. 退職金とiDeCoを同時期に一時金受取すると控除が減ります。先にiDeCo、5年以上後に退職金を受け取ると手取りを最大化できます。
2025.10.09
男性60代
“退職金はどのように受け取るのが一般的ですか?手続きや受け取り方法を知りたいです。”
A. 退職金の受け取りは「一時金」「年金」「併用」の3種類。税制優遇のある一時金か、定期収入を得られる年金かで負担が変わります。確定拠出年金との受取時期も重要で、最適な方法は個人の状況により異なります。
2024.08.08
男性
“企業DCは個人にとって節税にならないので、iDeCoの方がいいのでしょうか”
A. 会社負担の企業型DCは社会保険料も減り節税効果が大きい。まずDC上限まで拠出し、不足分をiDeCoまたはマッチング拠出で補うのが合理的。