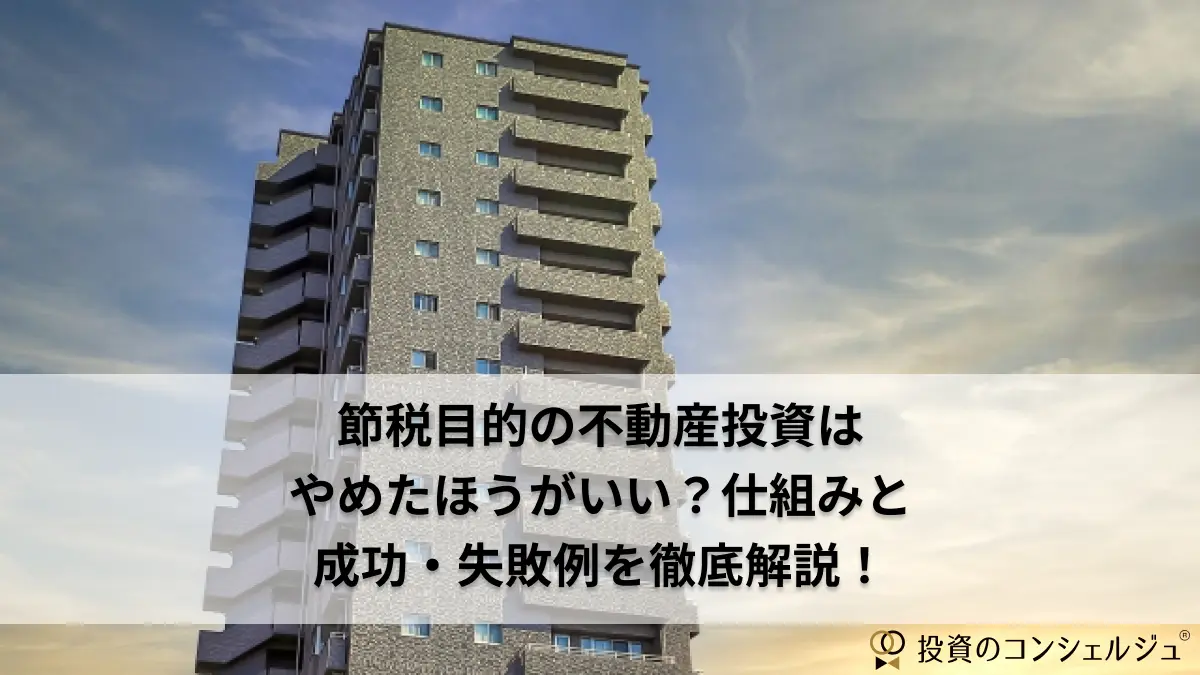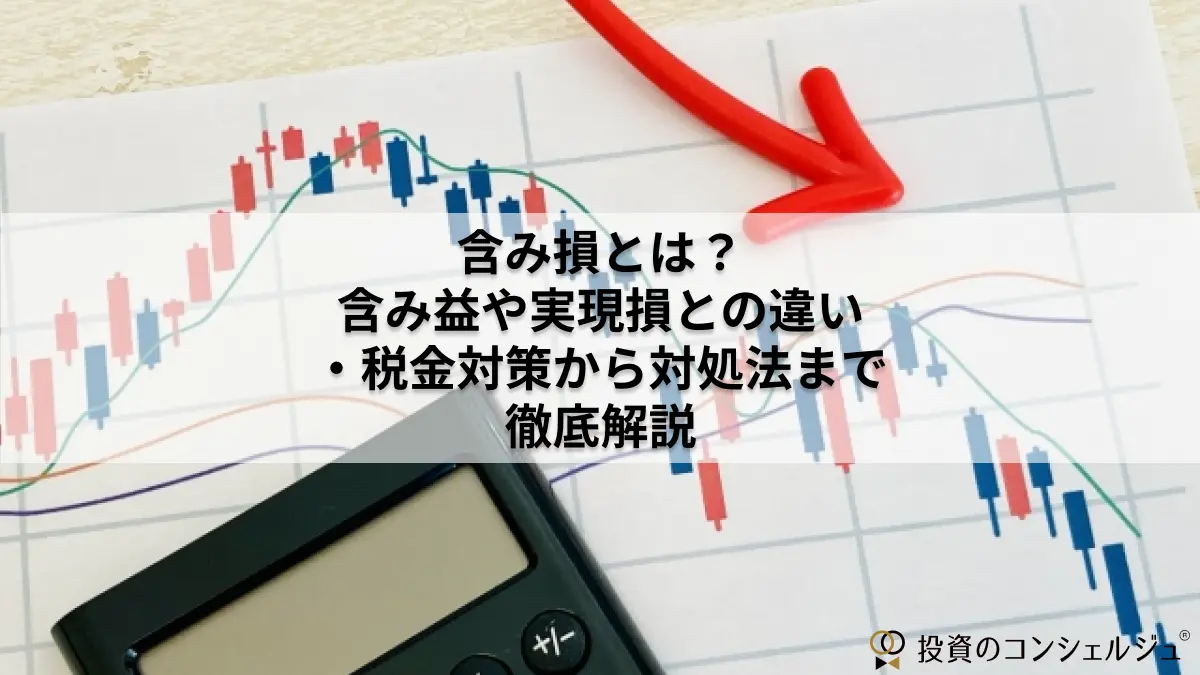資産運用の損金と損益通算とは?法人・個人の違いと投資損失の取り扱いを徹底解説

資産運用の損金と損益通算とは?法人・個人の違いと投資損失の取り扱いを徹底解説
難易度:
執筆者:
公開:
2025.08.05
更新:
2025.12.30
投資損失の取り扱いは「法人は損金」「個人は損益通算」と一言で片づけられがちですが、実際には制度改正の影響で適用範囲が年々変わります。とりわけ令和3年(2021年)の海外中古不動産に関する減価償却規制は要注意です。さらに欠損金を最長10年繰り越して課税所得をゼロにできる仕組みも、条件を満たさなければ機能しません。本記事では法人と個人で異なる節税ルールを整理し、見落としやすい実務上のポイントを解説します。
資産運用損失の基礎:損金と経費の違いを正しく理解する
資産運用における損失が、法人・個人それぞれの税務にどのような影響を与えるのでしょうか。その理解の出発点となるのが、法人税法上の「損金」と、会計上の「費用」、さらには個人税制における「必要経費」や「損益通算」の違いです。
本章では、法人税における損金の定義と計算の仕組みを押さえたうえで、個人投資家との制度的な違いを整理します。
法人税法における「損金」の定義
法人税法における損金とは、法人がその事業年度に得た益金(課税対象の収益)から控除できる支出や損失の総称です。法人税法第22条第1項において、「課税所得=益金-損金」と定義されており、損金の範囲は次の3つで構成されています(同条第3項)。
- 原価の額:売上に対応する売上原価や完成工事原価など
- 費用の額:販売費・一般管理費など、一定期間に対応する支出
- 損失の額:貸倒れや資産の評価損など、非資本取引に由来する損失
これらを合算したものが「損金」となり、たとえば営業活動にかかる支出や、有価証券の売却損なども、適切な経理処理と要件を満たせば損金として認められます。つまり、法人は原則として「事業に関連する損失」であれば、投資による損失も本業の利益から差し引くことが可能です。
会計上の費用との違いと損金不算入項目
会計上では費用として処理している支出でも、法人税法上は損金に算入されないことがあります。これを「損金不算入」といい、代表例として以下が挙げられます。
- 交際費の一部(上限超過分)
- 法人税・住民税そのもの
- 一部の寄附金や罰金
- 法定外の引当金
- 要件を満たさない資産の評価損(含み損)
これらの存在により、会計上の利益と税務上の課税所得は一致しません。そのため、法人は税務申告にあたり「別表四」で会計上の利益を税務ベースに調整する必要があります。
課税所得の計算フローと損金の役割
法人税の計算は、以下のようなフローで進みます。
- 会計上の利益を計算(収益-費用)
- 税務上の益金・損金に応じて加算・減算調整
- 調整後の課税所得に法人税率を乗じて税額を算出
この過程で、損金算入できる支出が増えれば、その分だけ課税所得が減少し、納税額を抑えることができます。たとえば、1,000万円の利益に対して100万円分の追加損金があれば、課税所得は900万円となり、法人税実効税率が30%とすれば約30万円の節税が可能になります。
このように、法人の節税対策とは、いかにして「会計上の費用」を「税務上の損金」として確実に認めてもらうかという作業でもあります。
損金計上が法人に与える実務的効果
適切な損金計上は、単なる節税ではなく、法人のキャッシュフロー改善にも直結します。特に、減価償却費や固定資産除却損・評価損など、現金の支出を伴わない「非資金支出型」の損金は、納税負担を軽減しつつ現金を手元に残すことができるため、経営上大きなメリットがあります。手元に残ったキャッシュを再投資に回すことで、さらなる事業拡大が可能になるからです。
個人には「損金」概念がないことに注意 一方で、個人税制においては「損金」という概念は登場しません。個人事業主であれば「必要経費」を所得から差し引くことができますが、これは法人税法上の損金とは別の制度です。また、給与所得者など一般の個人投資家には、そもそも経費控除の範囲が厳しく制限されています。
所得税は区分計算が原則
個人の所得税は、以下のように10種類の所得区分に分けて計算され、それぞれの区分内で課税が行われます。
- 事業所得
- 不動産所得
- 給与所得
- 譲渡所得
- 雑所得 など
このため、株式やFXで損失が出ても、それを給与所得など他の所得から控除することは原則できません。投資の失敗による赤字が、生活基盤である給与の税金計算にまで影響しないように設計されているとも言えます。
損益通算や繰越控除の活用に限られる
個人の投資損失は、次のような限定的な制度で救済されます。
- 株式の譲渡損失と配当所得の通算(分離課税内)
- 譲渡損失の3年間繰越控除
- 先物取引に係る損失の通算・繰越(FXなど)
- 不動産所得の赤字と他所得の通算(一定条件下)
たとえば会社員が株式投資で100万円の損失を出しても、その金額を給与所得から直接差し引くことはできません。ただし、上場株式の配当との通算や、3年間の損失繰越が可能な場合もあるため、確定申告を通じて適切な手続きを行うことが重要です。
法人における損金算入が認められる投資活動とその要件
法人が行う資産運用において発生する損失や費用の多くは、一定の要件を満たせば法人税法上の「損金」として認められます。損金算入が認められることで、課税所得を圧縮し、法人税の負担を軽減することが可能です。
ただし、すべての投資損失が無条件で損金に算入できるわけではなく、税法上の要件や会計処理の整合性が求められます。以下では、法人の代表的な投資活動ごとに損金算入の可否と注意点を整理します。
有価証券の売却損(株式・債券・投資信託等)
法人が保有する有価証券(上場株式、社債、公社債投資信託など)を売却して損失が出た場合、その譲渡損は原則として当期の損金に算入されます(法人税法第61条の2)。
損金算入の条件と実務上の留意点
- 会計上の損金経理が必要:損益計算書に適切に損失を計上することが損金算入の前提です。
- 売却による実現損のみ対象:含み損の段階では原則損金にはなりません。
- 評価損の例外あり:価値が著しく下落した場合(例:上場廃止や災害等)には、期末に評価損として損金算入が認められることがあります。
- 完全子会社株式等の例外:一定の関係会社株式については評価損が損金不算入となる場合があります。
具体例
取得価額1,000万円の株式を600万円で売却した場合、400万円の譲渡損が発生し、損益計算書に計上すればその年の損金とすることが可能です。
投資関連の費用(投資顧問料・信託報酬・借入利息等)
法人が投資を行うにあたり発生する手数料や利息なども、事業活動に関連する支出として、原則損金算入が認められます。
損金算入される主な費用
- 投資顧問会社に支払う投資助言報酬
- 投資信託等に関わる信託報酬
- 運用資金調達のための借入利息
これらは法人税法22条3項2号に定められる「販売費及び一般管理費その他の費用」として取り扱われます。
具体例
投資顧問料50万円(税込)を支払っている法人は、その全額を当期の損金に算入可能です。 また、1,000万円の運用資金を年利2%で借り入れた場合の利息20万円も、損金として計上可能です。
固定資産の除却損・一部の評価損(不動産・設備等)
不動産や設備などの固定資産について、除却や災害による評価損が生じた場合も、損金算入が認められるケースがあります。
除却・廃棄による損失
帳簿価額の全額を「除却損」として損金に計上可能。たとえば、帳簿価額2,000万円の建物を解体・廃棄した場合、その2,000万円は損金とすることができます。
評価損が認められる例外的ケース
原則として、資産価値の通常の減少(摩耗・古化)は減価償却で対応し、評価損にはできません。ただし、以下の場合は例外的に損金算入が認められます。
- 災害等による損傷
- 急激な市場変化による著しい陳腐化
その根拠を示す鑑定評価書・災害証明書等を添付することが実務上必須です。
デリバティブ損失・為替差損(時価評価含む)
デリバティブ取引(先物、オプション、スワップ等)や外貨建取引による損失についても、法人税法上の規定に従い、多くの場合で損金算入が認められます。
デリバティブの時価評価損益は「みなし決済」が原則
法人税法第61条の5により、事業年度末に未決済のデリバティブ取引がある場合には、その評価損益をみなし決済したものとみなして損益計上する必要があります。
- 含み損→損金算入
- 含み益→益金算入
具体例
期末時点で500万円の含み損がある場合、500万円は損金算入。逆に含み益が500万円あれば、益金として課税対象となります。
為替差損も損金算入の対象
法人税法第61条の9に基づき、外貨建資産・負債を期末時に円換算した結果生じる差損益についても、原則当期の損益として処理されます。
- 円高による評価損→損金算入
- 円安による評価益→益金算入
ただし、金銭債権の評価損については「貸倒引当金繰入」による処理となる場合があります。
損金算入の実務対応:計上処理と証憑がカギ
これらの投資損失を損金として認めてもらうためには、次の2点が重要です。
- 会計上の適切な処理(損金経理)
- 税務調整および明細書の整備(別表調整、証拠書類の保存)
評価損や除却損など、税務署が否認しやすい取引については特に、計上根拠の明確化(契約書・証明書・取締役会議事録等)を徹底することが、節税効果を確実に享受するためのポイントです。
損金算入が否認されやすい投資活動と調査リスク
前述のように法人の投資損失は幅広く損金にできますが、内容によっては税務調査で損金算入を否認されるケースもあります。とりわけ注意すべきは、形式的・恣意的な損失計上や、会社の損失を個人の損失と混同するようなケースです。ここでは税務上問題視されやすい項目と、そのリスクについて解説します。
実態のない評価損・仮装経費
経済的実態に乏しい損失計上は、税務上否認される代表例です。一つは前述した資産の評価損で、法律の要件を満たさない任意評価減は損金算入が認められません。
例えば、市場価格が多少下落した程度で有価証券の評価損を計上したり、耐用年数途中の固定資産を十分使用可能にもかかわらず評価減計上したりすると、税務調査で否認される可能性が高いです。また、架空経費(仮装経費)の計上も論外です。
存在しない業務委託費や架空の利息支払いなどを費用計上するのは明確な脱税行為であり、発覚すればその経費は全額損金不算入となるだけでなく、重加算税など厳しいペナルティが科されます。
具体例
実態のないコンサルティング契約をでっち上げ、年間300万円の手数料を支払ったことにして損金計上していた場合、税務署の調査で契約実態や支払事実がないと判明すれば、この300万円は損金として認められません。
そればかりか仮装隠蔽行為とみなされれば35%(場合により40%)の重加算税が追徴され、最悪の場合は青色申告の取り消し処分まで受けるリスクがあります。違法な節税策(脱税)は決して行わないことが肝要です。
役員個人資産との混同(役員貸付等)
法人の資産と役員・オーナー個人の資産が混在しているケースも、税務上問題視されます。典型例は役員への貸付金や立替経費です。
例えば会社が役員個人の株式投資資金を肩代わりして貸し付け、その投資で損失が出たからといって会社帳簿上貸倒損失を計上するような場合です。
一見すると会社の損失のように見えますが、実質的には役員個人の損失を会社経由で計上しているに過ぎず、税務署はこれを役員賞与(みなし給与)や寄附金等とみなして損金不算入とする可能性があります。役員貸付金の貸倒処理は特に調査で注目されるポイントであり、親族間・同族会社間の金銭や資産のやり取りは行為計算否認規定(法人税法132条)によって経済合理性を厳しくチェックされます。
注意点:会社名義の資金を役員やその家族の私的投資に流用しないこと、やむを得ず役員に貸付を行う場合も社内手続や契約書の整備、利息の設定等をきちんと行い、常識的な範囲に留めることが重要です。役員個人の損失を会社で肩代わりする形になると、法人税だけでなく役員個人への所得税(雑所得や給与課税)問題にも波及しかねません。
親族・関連会社への形式的投資や貸付
同族関係者(親族やオーナーの関連会社)への資金移動も慎重な対応が必要です。例えば、実質的に回収する気のないグループ内会社への貸付金、あるいは親族経営の事業への形だけの出資などが該当します。
これらは税務上、会社利益の社外流出や資金の移転とみなされ、損失計上が否認されるケースがあります。関連当事者間取引は客観的な第三者取引と比べ、損失が生じた場合に恣意的な操作が疑われやすいからです。例えば同族会社間で高額な社債を発行・償還して損失を出した場合、それが実質的に租税回避スキームと判断されれば、損金算入が認められないだけでなく、経済的利益の供与として寄附金認定されるリスクもあります。
さらに悪質な場合、税務当局は推計課税の権限を行使することがあります。取引の実態を解明する過程で帳簿や証憑が不備・欠如していると判断されれば、当局が推計により所得を算定して課税することも法的に可能です(国税通則法に基づく更正)。
こうした事態を防ぐためにも、証憑書類の適切な保存が不可欠です。法人は原則として確定申告期限の翌日から7年間、帳簿書類や領収書を保存する義務があります。
特に同族間取引や貸借については契約書・議事録・送金記録などを完備し、少なくとも7年(繰越欠損金の発生年度に関わるものは最長10年)は保存しておきましょう。
損金算入がもたらす節税メリットと繰越欠損金の活用
適切に損金計上を行うことは、その年度の法人税負担を軽減し企業のキャッシュフローを改善します。さらに損失が大きく当期で控除しきれない場合でも、繰越欠損金制度を活用することで将来の黒字と相殺することが可能です。ここでは損金算入による節税効果と、欠損金の繰越控除について解説します。
資産管理会社の活用法についてはこちらの記事をご参照ください。
当期課税所得の圧縮効果とキャッシュフロー
法人が損金算入できる支出や損失を計上すると、その分だけ当期の課税所得(益金−損金)が減少します。課税所得が減れば法人税額も減少するため、手元に残るキャッシュが増えるという直接的な節税効果が得られます。
特に現金流出を伴わない損金はキャッシュフロー上有利です。例えば減価償却費は資産の簿価配分であり、当期に現金支出はありませんが、損金に算入することでその分だけ納税額を減らせます。
同様に、評価損や繰入経費などもキャッシュアウトなしに節税効果をもたらします。一方、保険料のように支出を伴う節税策では支出額以上の税減少はないため、損金計上=即節税と短絡的に考えず、事業上の必要性とキャッシュフローへの影響を総合的に判断することが大切です。
青色申告・欠損金繰越(最長10年)の要件
法人がある事業年度に欠損金(赤字)を計上した場合、その金額は将来の黒字所得と相殺(控除)することが可能です。これを繰越欠損金の繰越控除といい、適用を受けるには青色申告を行っていることが前提となります。
具体的には、「青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金」は翌期以降に繰り越せます。繰越可能期間は原則として欠損金発生年度開始の日から10年間(平成30年4月1日以後開始事業年度の場合)となっています。
繰越控除を受けるための主な要件は以下のとおりです。
- 青色申告の適用を受けていること(事前に税務署へ青色申告承認申請書を提出済み)
- 欠損金が発生した事業年度から継続して確定申告を提出していること(欠損を出した後、たとえ利益がなくても無申告期間があると繰越不可)
- 帳簿書類を適切に保存していること(欠損金の内容を証明できるよう7年間の保存義務、※繰越期間延長に伴い10年に延長)
例えば、2025年度に1,000万円の赤字(欠損金)が発生した中小企業は、2026~2035年度までの各年度でその欠損金を順次控除できます。仮に2026年度に500万円の黒字が出れば、繰越欠損金と相殺して課税所得を0にでき、残り500万円の欠損金はさらに繰り越します(最長10年。
このように赤字の税効果を将来に繰り延べできる点で、繰越欠損金制度は重要な節税手段です。なお制度利用には確定申告書への繰越欠損金に関する明細の添付等が必要なので、申告漏れに注意しましょう。
黒字化年度への通算戦略と留意点
繰越欠損金は将来の税負担を軽減する重要な資産ですが、ただ漫然と繰り越せばよいわけではありません。企業規模による控除限度額の違いや、有効期限、さらには組織再編時の制限など、ルールを正しく理解していないと、せっかくの節税メリットを失う可能性があります。ここでは、将来の黒字と相殺する際の戦略と注意点を解説します。
####控除限度額:中小企業は全額相殺できるが大企業は50%制限あり
繰越欠損金と黒字を相殺する際、その上限ルールは企業規模によって異なります。資本金1億円以下の中小法人などは、所得金額の100%まで欠損金を控除できるため、過去の赤字分だけその年の法人税をゼロにすることも可能です。一方、資本金が1億円を超える大企業は、繰越控除前の所得の50%までしか控除できない制限があります。大企業の場合、たとえ多額の欠損金が残っていても、単年度の利益の半分には必ず課税される仕組みになっている点に注意が必要です。
####有効期限:10年の時効内に使い切るための利益計画
繰越欠損金には「10年間」という有効期限があります。この期間を過ぎると、残っている欠損金は消滅し、二度と利用できなくなります。基本的には早期に黒字を計上して欠損金を使い切るのがセオリーですが、将来的に大きな利益が見込まれる場合は、あえて費用の計上タイミングを調整するなどして、最も税効果が高くなる時期に欠損金をぶつける戦略も考えられます。期限切れによる失効を防ぐためにも、中長期的な利益計画に基づいた管理が欠かせません。
####組織再編時の注意:M&Aや株主変更で欠損金が消滅するリスク
欠損金がある会社を買収したり、株主が大きく入れ替わったりする場合には注意が必要です。不当な租税回避を防ぐため、特定の要件下でのM&Aや、事業内容が著しく変わるようなケースでは、過去の欠損金の引き継ぎや利用が制限されるルールが存在します。意図せず欠損金が切り捨てられる事態を避けるため、組織再編や事業承継を行う際は、事前に税理士などの専門家へ相談し、欠損金の取り扱いを入念に確認することが重要です。
個人の所得区分と損益通算・繰越控除の全体像
個人の税金計算において最も重要な特徴は、所得をその性質に応じて10種類に区分し、それぞれ個別に計算を行う点です。これを「所得区分」と呼びます。原則として、それぞれの区分で税金を計算しますが、例外的に赤字を他の所得と相殺できる「損益通算」や、損失を翌年以降に持ち越せる「繰越控除」という仕組みが存在します。ここでは、所得の分類方法と、収入と所得の違い、そして投資家が知っておくべき課税ルールの全体像を解説します。
個人の所得区分と収入・所得の違い
まず押さえておきたいのが、「収入」と「所得」は全く異なる概念であるという点です。
収入とは、給与の額面や売上高など、入ってくるお金の総額を指します。一方、所得とは、その収入から必要経費や法で定められた控除額を差し引いた、いわば「税金の対象となる利益」のことです。
所得金額=収入金額-必要経費(または給与所得控除などの法定控除)
日本の所得税法では、この所得を以下の10種類に分類しています。
- 利子所得(預貯金や公社債の利子)
- 配当所得(株式の配当金や投資信託の分配金)
- 不動産所得(土地建物の賃貸収入)
- 事業所得(商売や事業による所得)
- 給与所得(会社からの給料や賞与)
- 退職所得(退職金など)
- 山林所得(山林の伐採や譲渡による所得)
- 譲渡所得(不動産や株式、資産の売却益)
- 一時所得(懸賞金や生命保険の一時金など)
- 雑所得(公的年金、副業収入、暗号資産取引など他の9つに当てはまらないもの)
金融所得の総合課税・分離課税・申告不要の整理
投資によって得られる利益(金融所得)にかかる税金は、その種類や受け取り方によって「総合課税」「申告分離課税」「源泉分離課税」のいずれかに分類されます。また、確定申告をせずに済ませる「申告不要制度」を選択できるケースもあります。どの課税方式を選ぶかによって税率や損益通算の可否が変わり、最終的な手取り額に直結するため、主要な金融商品のルールを整理しておきましょう。
利子所得:預金は申告不可だが債券利子は損益通算が可能
銀行預金の利息などは、受け取り時に20.315%の税金があらかじめ天引きされる「源泉分離課税」であり、これで納税が完結するため確定申告はできません。一方、国債や社債(特定公社債等)の利子は「申告分離課税」の対象です。原則は源泉徴収されますが、あえて確定申告を選択することで、株式等の譲渡損失と損益通算することが可能になります。
配当所得:申告不要・総合・分離から有利なものを選択
上場株式等の配当金は、受け取り時に税金が天引きされているため、そのまま何もしない「申告不要制度」を利用するのが一般的です。ただし、確定申告をすることも可能です。その場合、一定の税額控除を受けるために「総合課税」を選ぶか、または株式等の売却損と相殺(損益通算)するために「申告分離課税」を選ぶか、自身の状況に合わせて有利な方法を選択できます。
株式等の譲渡所得:特定口座なら申告不要だが損失時は申告が必要
株式や投資信託の売却益は、給与などの他の所得とは切り離して税金を計算する「申告分離課税」となります。証券会社の「源泉徴収ありの特定口座」を利用していれば原則として確定申告は不要ですが、損失が出ている場合などは、あえて申告することで配当所得との損益通算を行ったり、使いきれない損失を翌年以降に繰り越したりすることが可能です。
損益通算と損失繰越の基本ルール(個人)
個人において、ある区分の赤字を他の区分の黒字と相殺(損益通算)できるのは、以下の4つの所得に限られます。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得(土地建物や株式を除く、総合課税の対象となるもの)
これら以外の、給与所得や雑所得(副業や暗号資産など)で生じた赤字は、他の所得と通算できず、その年で切り捨てとなります。
ただし、投資に関しては特例措置があります。
上場株式等やFX・先物取引などの損失は、それぞれの区分内(申告分離課税のグループ内)でのみ損益通算が可能です。さらに、確定申告を行うことで、使い切れなかった損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益から控除することができます。
また、事業所得や不動産所得で青色申告を行っている場合も、損益通算しきれなかった損失を3年間繰り越すことが認められています。このように、適切な申告を行うことで、税負担を軽減できるケースがあることを覚えておきましょう。
〈個人編〉投資損失の税務処理(損益通算・繰越控除)と制限
次に、個人投資家における投資損失の取り扱いを見ていきましょう。個人の場合、法人のような損金算入はできませんが、所得税法上定められた範囲で損益通算(同一年の利益と損失を相殺)や損失の繰越控除が認められています。ただし、適用可能な所得の種類や通算条件には厳しい制限があります。主なケースごとに整理します。
不動産赤字の損益通算の可否についてはこちらのQ&Aもご参照ください。
上場株式・投信の譲渡損と分離課税内通算
上場株式や投資信託で発生した損失は、原則として給与所得などとは相殺できませんが、金融商品同士での通算や、将来の利益へ持ち越す特例が認められています。これらを活用するには、確定申告において適切な手続きを行う必要があります。ここでは、株式投資の損失を無駄にしないための3つのステップと、見落としがちな注意点を解説します。
銘柄間の通算:まずは株式等の売買損益同士を相殺する
株式や公募株式投資信託の売買損益は「申告分離課税」の株式等譲渡所得等に区分され、まずはこのグループ内で利益と損失を計算します。
たとえば、同じ年に株式Aで50万円の利益、株式Bで80万円の損失が出た場合、これらを相殺して「30万円の損失」として扱います。複数の証券口座を持っている場合でも、確定申告をすることで口座をまたいだ通算が可能です。これにより、利益が出ている口座の税金を減らすことができます。
配当との通算:申告分離を選べば配当税を取り戻せる
株式同士で通算してもなお損失が残る場合、次に検討すべきなのが「配当所得」との相殺です。
上場株式等の配当金は、確定申告時に「申告分離課税」を選択することを条件に、株式の譲渡損失と損益通算することが認められています。これにより、配当受け取り時に源泉徴収されていた約20%の税金を取り戻す(または軽減する)ことが可能です。ただし、総合課税を選んで配当控除を受ける場合は、この損益通算は使えないため、どちらが有利か試算する必要があります。
繰越控除:使いきれない損失は確定申告で3年間持ち越す
配当と通算してもまだ損失が残っている場合、その損失を翌年以降に繰り越すことができます。これを「譲渡損失の繰越控除」といい、最長3年間にわたって将来の株式譲渡益や配当所得から控除できます。
この制度を利用するための絶対条件は「確定申告」です。損失が出た年に申告書(付表)を提出するのはもちろん、その後取引がない年であっても、損失を繰り越している間は毎年連続して確定申告を行い続ける必要があります。1年でも申告を忘れると、繰り越していた権利が消滅してしまうので注意が必要です。
NISAや手続きの注意点:通算できないケースを知っておく
すべての株式損失が通算できるわけではありません。特に注意が必要なのがNISA(少額投資非課税制度)です。NISA口座内で発生した損失は「税務上はないもの」とみなされるため、他の口座の利益と損益通算することも、繰越控除することもできません。
また、証券会社を通さない相対取引などの損失も特例の対象外です。これらの制度を活用する際は、対象となる取引かどうかを確認し、必ず期限内に確定申告を行うようにしましょう。
仮想通貨・FXの雑所得扱いと通算不可
仮想通貨(暗号資産)やFX取引で生じた利益は、原則として「雑所得」に区分されます。しかし、ひとくちに雑所得といっても、その取引内容によって「総合課税」と「申告分離課税」に分かれ、損失が出たときの扱いは大きく異なります。ここでは、仮想通貨の厳しい損失ルールと、FXにおける国内・海外業者の税制格差について解説します。
仮想通貨(暗号資産):損失は切り捨てられ、節税には使えない
ビットコインなどの仮想通貨取引で生じた損益は、原則として「総合課税の雑所得」に該当します。この区分における最大のデメリットは、損失が生じても他の所得と一切相殺できないことです。
たとえば、会社員が仮想通貨で100万円の大損失を出したとしても、その穴を給与所得から埋める(損益通算する)ことはできません。また、株式や国内FXのような繰越控除の制度もないため、その損失は翌年に持ち越せず、税務上「なかったもの」として完全に切り捨てられます。
国内FXの特例:先物取引グループ内なら通算・繰越が可能
同じFXでも、国内の証券会社やFX業者(金融商品取引業者等)を利用した取引は扱いが異なります。これらは「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、以下の優遇措置が受けられます。
- 損益通算:FXの損失を、日経225先物や商品先物など、他の「先物取引等」の利益と相殺できます(株式とは通算できません)。
- 繰越控除:通算しきれない損失がある場合、確定申告を条件に翌年以降3年間繰り越して、将来の先物取引等の利益から控除できます。
海外FXの注意点と税務リスクを踏まえた投資判断
注意が必要なのは、海外のFX業者を利用した場合です。これらは日本の金融商品取引法の登録を受けていないため、国内FXのような申告分離課税の特例は適用されず、仮想通貨と同じ「総合課税の雑所得」となります。
つまり、海外FXでどれだけ大きな損失を出しても、国内FXの利益と相殺することはできず、繰越控除も認められません。「ハイレバレッジで利益が出やすい」と言われる海外FXですが、負けたときの税務上の救済措置は一切ないというリスクを十分に理解して資金管理を行う必要があります。
不動産投資赤字と総合課税通算の可否
不動産投資(賃貸収入)は、個人の所得区分では「不動産所得」に該当します。不動産所得の計算上赤字(経費が収入を上回る)が生じた場合、その損失は給与所得など他の所得と損益通算が可能です。
これは、所得税法上損益通算が認められる4種類の所得(不動産・事業・譲渡・山林)の一つに不動産所得が含まれているためです。
したがって、例えばサラリーマンがアパート経営をしていて賃貸収支が年間100万円の赤字となった場合、給与所得の金額からその100万円を控除することができます。結果として課税所得が圧縮され、所得税・住民税の負担が軽減されることになります。不動産投資の減価償却等による節税はこの仕組みを利用した典型例です。
ただし、不動産所得の損失であれば何でも通算できるわけではなく、一部例外が設けられています。代表的なものは次のとおりです。
- 別荘などの趣味的資産に係る損失:例えば自家用の別荘やクルーザーを他人に貸し付けた場合の損失は通算不可(それ自体が生活に通常必要でない資産のため)。
- 土地取得資金の利子に係る損失:不動産所得の計算上、土地購入の借入利息相当額については他の所得と通算できません。これは高額な土地購入による赤字(利払い)で給与所得を圧縮することを防ぐ趣旨の規定です。
- 海外中古不動産の減価償却損:令和3年(2021年)以降、外国中古建物を購入して加速償却するスキームが規制され、簡便法等で計算した減価償却費による損失は通算が認められなくなりました。高額な海外中古物件を取得し短期間で大きな減価償却費を計上して給与所得と相殺する節税策が多用されたため、税制改正で対策が講じられたものです。
以上の特例を除けば、通常の国内不動産投資の赤字は他の所得(給与・事業・配当等の総合課税所得)と自由に通算できます。
実際、多くの高所得者が不動産投資による減価償却で所得圧縮を図っているのはこのためです。例えば年収1,000万円の給与所得者が木造アパートに投資し、減価償却やローン金利で年間200万円の赤字を出せば、課税所得は実質800万円に減り大幅な節税になります。
もっとも、昨今は上述の海外不動産スキーム規制などもあり、税務当局も不動産所得の赤字には敏感です。証拠書類の整備(減価償却計算根拠や借入金利の明細等)や投資の実態(実際に賃貸しているか等)について、調査で確認を求められてもよいよう準備しておくべきです。
よくある質問(FAQ)
2025.06.11
女性70代
“海外自動ai投資得た利益分は税金20.315パセントは先払いが正しいですか ”
A. 海外AI投資で利益から税金が差し引かれる仕組みは通常の日本の制度とは異なります。詐欺の可能性も否定できないため、慎重に確認し、公的機関に相談をおすすめします。
2026.02.09
男性40代
“分離課税の税率を教えて下さい。”
A. 金融所得の分離課税は合計20.315%(所得税等15.315%+住民税5%)。申告分離も源泉分離も税率は同じです。
2026.02.09
男性40代
“確定申告で配当控除を適用させる方法を教えてください。”
A. 配当控除は総合課税で申告した場合のみ使えますが、売却損がある年や高所得の場合は申告分離課税や申告不要の方が有利なこともあります。所得水準と損益状況に応じて課税方式を選ぶことが重要です。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連する専門用語
損金
損金とは、法人税の計算上、企業の所得から控除できる費用のことを指す。具体的には、給与、仕入原価、広告宣伝費、減価償却費などの事業に直接関連する支出が該当する。損金に計上できるかどうかは税法により定められており、計上可能な費用を適切に処理することで課税所得を抑えることができる。一方で、税務上の損金と会計上の費用が一致しない場合もあり、適切な管理が求められる。
益金
益金とは、法人税の計算において、企業の所得に算入される収益のことを指す。売上高や営業外収益、資産の売却益、受取配当金などが含まれる。益金は損金と対になる概念であり、最終的な課税所得を決定する重要な要素となる。法人の税負担を適切に管理するためには、益金と損金の区分を正しく理解し、税務処理を行うことが求められる。
損金算入
損金算入とは、企業が支払った経費のうち、税務上の所得計算において課税対象から控除できる金額のことです。例えば、事業活動に必要な経費や接待交際費の一部は損金算入の対象となります。損金算入により、企業の課税所得が減少し、納める法人税が軽減されます。
必要経費
必要経費とは、収入を得るために直接かかった費用のことを指し、確定申告などで所得から差し引くことができる支出です。たとえば、フリーランスや自営業者が事業を行う際に使った交通費、通信費、仕入れ代、人件費、事務所の家賃などが該当します。 これらは税務上、所得を正しく計算するために必要な項目とされており、収入から必要経費を差し引いた残りが「課税所得」となります。必要経費として認められるには、「収入を得るために必要だった」という合理的な理由があり、領収書や記録で裏付けられることが求められます。 正しく計上することで税負担を適正化でき、節税にもつながるため、特に個人事業主や副業をしている人にとっては重要な考え方です。
損益通算
投資で発生した利益と損失を相殺することで、課税対象となる利益を減らす仕組みのことです。たとえば、株式投資で50万円の利益が出た一方、別の取引で30万円の損失が発生した場合、損益通算を行うことで、課税対象となる利益は50万円から30万円を引いた20万円になります。この仕組みにより、納める税金を減らすことが可能です。 損益通算が適用されるのは、同じ「所得区分」の中でのみです。たとえば、株式や投資信託の譲渡損益や配当金などは「株式等の譲渡所得等」に分類され、この範囲内で損益通算が可能です。ただし、不動産所得や給与所得など、異なる所得区分間では基本的に通算できません。 さらに、株式投資の損失は、損益通算後も控除しきれない場合、翌年以降最長3年間繰り越して他の利益と相殺できます。これを「繰越控除」と呼び、投資初心者にとっても節税に役立つ重要なポイントです。
繰越控除
繰越控除とは、特定の損失や控除額を翌年度以降に持ち越し、将来の所得から控除できる税制上の仕組みを指す。代表的なものとして、青色申告の純損失の繰越控除があり、一定期間内に発生した損失を翌年以降の利益から差し引くことができる。これにより、赤字企業でも将来の黒字化に伴い税負担を軽減できるメリットがある。ただし、適用には一定の要件があり、期限内に申告する必要がある。
減価償却
減価償却とは、固定資産の購入価格をその使用可能年数にわたって経済的に分配する会計処理の方法です。企業が機械や建物、車両などの固定資産を購入した際に、これらの資産は使用することで徐々に価値を失います。減価償却を行うことで、資産のコストをその寿命にわたって費用として計上し、その結果として企業の財務報告が実態に即したものになることを目指します。 減価償却には様々な方法がありますが、一般的なものに直線法、定率法、数字和法があります。直線法はもっとも単純で、資産の耐用年数にわたって均等に費用を計上します。定率法は残存価値を基に毎年一定の割合で費用を計上し、数字和法では耐用年数の初年度に最も多くの費用を計上し、年数が経過するにつれてその額を減らしていきます。 減価償却は税務上も重要で、企業は減価償却費を経費として計上することで課税所得を減少させることができます。このため、適切な減価償却方法の選択と計算は、企業の税負担の管理にも直接関連しています。
繰越欠損金
繰越欠損金とは、ある年の所得が赤字(損失)になった場合に、その損失分を翌年以降の黒字と相殺するために使える税務上の制度です。法人税や所得税において適用され、たとえば前年に100万円の赤字があり、今年に150万円の黒字が出た場合、その赤字分を差し引いた50万円だけが課税対象となります。 これにより、利益が出た年の税負担を軽減することができ、長期的に安定した経営や資産形成を支援する効果があります。繰越できる期間は制度によって異なりますが、法人税では最長10年間、個人の青色申告では原則3年間とされています。損失が出ても将来の節税につながる可能性があるため、正確な記帳と申告が非常に重要です。
デリバティブ取引
デリバティブ取引とは、株式や為替、金利、商品(コモディティ)などの「原資産」の価格や数値の変動に基づいて、その将来の価値を取引する金融商品のことをいいます。「派生商品」とも呼ばれ、先物(フューチャーズ)、オプション、スワップなどの種類があります。この取引の特徴は、実際に原資産を売買するのではなく、将来の価格に対する「約束事」を売買する点にあります。たとえば、将来の為替レートを今のうちに決めておくことで、リスクを回避する「ヘッジ」として使われる一方、値動きを利用して利益を狙う「投機」目的でも利用されます。少ない資金で大きな取引ができる一方で、損失も大きくなる可能性があるため、リスク管理が非常に重要です。資産運用や企業のリスクコントロールに欠かせない取引形態のひとつです。
外国為替(為替)
外国為替(為替)とは、異なる通貨を交換する仕組みおよびその交換比率が経済活動や資産価値に影響を及ぼす関係全体を指す用語です。 この用語は、海外と関わる取引や資産評価を行う場面で必ず登場します。輸入や輸出といった企業活動だけでなく、外国株式や海外投資信託、外貨建て資産を保有する個人投資家にとっても、為替は価格変動の前提条件として存在します。円と他国通貨との関係が変化することで、同じ資産であっても円換算の価値や損益が変わるため、投資判断や成果の解釈に影響します。 為替が問題になるのは、「通貨を交換する瞬間」だけではありません。実際には、外貨建て資産を保有している期間全体にわたり、為替は見えない変動要因として作用します。そのため、投資の成果を考える際に、価格変動と為替変動が混同されやすく、判断を誤る原因になりがちです。たとえば、海外資産の評価額が増減した理由を、投資対象そのものの値動きだと理解していたものの、実際には為替変動の影響が大きかった、というケースは典型的です。 誤解されやすい点として、「為替は短期売買を行う人だけが意識すればよい」という思い込みがあります。しかし、為替は取引頻度に関係なく、外貨と関わる資産を持つ限り影響を及ぼします。長期投資であっても、円高・円安の局面によって最終的な成果が変わるため、為替を無視した評価は成り立ちません。為替は独立した投資対象である以前に、資産価値を測る尺度そのものの一部だと捉える必要があります。 また、「為替=相場」という理解も不十分です。為替は市場で形成される交換比率だけでなく、国や地域の通貨制度、決済慣行、国際的な資金移動の仕組みを含んだ概念です。為替レートはその結果として表れる数値であり、外国為替という言葉は、より広い関係性や構造を含んで使われます。この違いを意識しないと、為替変動の意味を単なる価格の上下としてしか捉えられなくなります。 外国為替を正しく理解することは、海外と関わる経済行動を評価する際の基礎になります。為替は利益を生む手段そのものではなく、資産や取引の価値を左右する前提条件として存在する概念であり、その位置づけを整理しておくことが重要です。
みなし決済
みなし決済とは、実際にお金のやり取りや売買が行われていない場合でも、税務上は「取引が成立した」と見なして課税の対象とする取り扱いのことです。 たとえば、保有している有価証券や資産を譲渡したことにして、含み益や含み損がある状態でも税金の計算を行うケースがあります。これは、相続や贈与、海外転出など、形式的には取引でなくても経済的に価値の移転があったと考えられる場合に適用されます。 みなし決済が行われると、たとえば譲渡益に対して所得税や住民税が課されることがあり、納税義務が発生します。税務上のルールとして非常に重要であり、知らずに適用対象となってしまうと想定外の納税が生じるため、専門家のアドバイスを受けることが望ましい分野です。
青色申告
青色申告は、個人事業主や不動産所得者、小規模事業者などが利用できる税務申告制度の一つで、一定の要件を満たすことで税務上のさまざまな特典を受けられる仕組みです。 具体的には、正確な帳簿を作成し、確定申告書を青色申告として提出することで、最大65万円の控除(複式簿記の場合)や、赤字を最長3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺できる制度などが利用可能です。また、家族への給与を必要経費として計上できる「青色事業専従者給与」も特徴の一つです。 青色申告を始めるには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。正確な記帳が求められるため、帳簿管理が重要ですが、節税効果が高く、多くの事業主に活用されています。
申告分離課税
申告分離課税とは、特定の所得について他の所得と分離して税額を計算し、確定申告を通じて納税する方式です。 主な対象となる所得は以下の通りです: - 譲渡所得: 土地や建物、株式などの譲渡による所得。 - 山林所得: 山林の伐採や譲渡による所得。 - 先物取引による所得: FXや商品先物取引による所得。 例えば、株式の譲渡所得については、他の所得と合算せずに分離して課税されます。また、上場株式等の配当所得についても、申告分離課税を選択することができます。
雑所得
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
先物取引
先物取引とは、将来のある時点に、あらかじめ決めた価格で特定の商品や資産を売買することを約束する取引のことです。対象となる資産には、原油や金などのコモディティ、株価指数、通貨などがあります。 この取引では、満期時に実際の商品を受け渡すケースはまれで、多くの場合、価格の変動による差額のみを決済する仕組みが一般的です。たとえば、「3か月後に1バレル100ドルで原油を購入する契約」を結び、実際の価格がそれより高くなっていれば、その差額が利益となります。 先物取引は、将来の価格を予想して利益を狙う投資手法(投機目的)として利用されるだけでなく、価格変動リスクを回避するためのヘッジ手段としても広く活用されています。たとえば、商品を扱う企業が仕入れ価格の急騰に備えるために、あらかじめ先物で価格を固定するといった使い方があります。 また、先物取引は証拠金を使った取引(レバレッジ型)であり、少ない資金で大きな金額の取引ができる反面、相場が予想と逆方向に動いた場合には、大きな損失を被るリスクもあります。 投資初心者にとってはやや難易度の高い取引ですが、仕組みを理解することで、コモディティや株価指数など多様な市場にアクセスできる手段となります。正しい知識とリスク管理を前提に、投資の選択肢として知っておくと役立ちます。
不動産所得
不動産所得とは、アパートやマンション、駐車場、土地などの不動産を人に貸すことで得られる収入のことをいいます。たとえば、持っているマンションの一室を他の人に貸して家賃を受け取ると、その家賃収入が不動産所得になります。ただし、収入から固定資産税や修繕費、管理費などの必要経費を差し引いた後の利益部分が実際の「所得」として計算されます。この不動産所得は、確定申告の際に他の所得と合わせて税金の対象になりますので、正しく計算して申告することが大切です。
実効税率
実効税率とは、名目上の税率ではなく、実際に支払った税額がどれだけの割合を占めているかを示す割合のことです。たとえば、税率が30%とされていても、各種控除や特例などを適用した結果、実際に支払った税金の割合が20%程度であれば、それが実効税率となります。 この数値は、企業の財務分析や投資判断においてとても重要です。なぜなら、同じ利益でも企業によって支払う税額が異なり、それが収益性やキャッシュフローに大きな影響を与えるからです。個人投資家にとっても、配当や売却益などにかかる税金の実効税率を知ることで、手取りの利益を正確に把握しやすくなります。名目の税率だけを見るのではなく、最終的にいくら税金が差し引かれるかという実態を理解することが、より現実的な資産運用につながります。
法人税
法人税とは、会社などの法人が事業を通じて得た利益に対してかかる税金で、国に納める国税のひとつです。個人にとっての所得税と同じように、会社の「もうけ」に対して課税されます。会社は1年間の売上から経費や人件費などを差し引き、最終的に残った利益、つまり「課税所得」を計算します。そして、その金額に応じて法人税が発生します。 法人税は、自分で税額を計算し、決算後に確定申告をして納める「申告納税方式」です。利益が出ていない赤字の年でも、申告手続きは必要です。税率は利益の大きさによって異なり、たとえば中小企業の場合、課税所得800万円までは軽減税率が適用され、法人税率は15%になります。それを超える部分には23.2%の税率がかかります。ただし、実際に会社が負担するのは法人税だけでなく、法人住民税や法人事業税なども含まれるため、すべてを合わせた負担割合、いわゆる「実効税率」はおおよそ20%〜35%ほどになることが一般的です。会社の所在地や規模によってこの数字は変動します。 また、日本では中小企業に対していくつかの税制上の優遇措置が設けられています。たとえば、軽減税率のほかにも、赤字となった年の損失を翌年以降の黒字と相殺できる「欠損金の繰越控除」や、一定の条件を満たした設備投資を行った場合に税金の一部が軽減される制度などがあります。こうした制度を活用することで、税負担を軽くしながら事業の資金を有効に活用することが可能になります。 このように、法人税は会社にとって基本的かつ重要な税金であり、利益が出たときにはもちろん、出なかったときにも申告義務があるという点を理解した上で、日々の経理や資金管理に取り組むことが大切です。
キャッシュフロー
お金の流れを表す言葉で、一定期間における「お金の収入」と「支出」を指します。投資や経済活動では特に重要な概念で、現金がどれだけ増えたか、または減ったかを把握するために使われます。キャッシュフローは大きく3つに分かれます。 1つ目は本業による収益や費用を示す「営業キャッシュフロー」、2つ目は資産の購入や売却に関連する「投資キャッシュフロー」、3つ目は借入金や配当などの「財務キャッシュフロー」です。 キャッシュフローがプラスであれば手元にお金が増えている状態、マイナスであれば減っている状態を示します。これを理解することで、資産の健全性や投資先の実態を見極めることができ、初心者でも資金管理や投資判断の基礎として役立てられます。
貸倒引当金
貸倒引当金とは、売掛金や貸付金など、将来的に回収できなくなる可能性のあるお金に備えて、あらかじめ費用として見積もっておくための会計処理です。企業は商品やサービスを売った時点で売上として計上しますが、必ずしも全額が確実に回収できるとは限りません。 そこで、万が一の未回収に備えて、あらかじめ一定の金額を「損失見込み」として費用計上しておくのが貸倒引当金です。これにより、将来に予想外の損失が発生した場合でも、企業の利益が大きくぶれるのを防ぐことができます。初心者の方にとっては、「まだ起きていないけれど、起こりそうな貸し倒れに備える貯金のようなもの」と考えるとわかりやすいでしょう。これは企業のリスク管理の一環であり、健全な会計処理として非常に重要な役割を持っています。
推計課税
推計課税とは、納税者が正確な申告をしていなかったり、帳簿や証拠書類が不十分だったりする場合に、税務署が外部の情報や業種平均、類似事例などをもとに所得や売上を「推計」し、それに基づいて税額を決定する制度です。 これは、申告内容の信頼性が低い場合でも公平な課税を行うために用意された手続きで、特に自営業者やフリーランスなどで記帳義務を怠ったケースに多く見られます。 たとえば、飲食店の売上に対してレジ記録がない、領収書が散逸しているなどの状況下では、類似店舗の平均的な売上や仕入れ比率を参考に、税務署が所得を推定して課税することになります。推計課税は本来の税額よりも不利になることがあるため、正確な帳簿と証拠資料の保存がとても重要です。
行為計算否認規定
行為計算否認規定は、納税者が行った取引が一見すると合法であっても、その主な目的が税金を不当に軽減することにあると判断された場合に、税務当局がその取引をなかったものとみなし、より適切な形に置き換えて課税できる制度です。法人税法132条などに規定されており、形式だけでなく実質に基づいて課税の公平性を確保するための強力な権限とされています。 この規定は、とくに同族会社をめぐる取引や、組織再編や資本関係を利用した節税スキームに対して適用されることが多くあります。たとえば、実態のない会社分割で欠損金を移転させて税負担を軽くしたり、含み益のある資産を簿価で子会社に移して損益通算を狙ったりする取引がその対象になります。また、本来は配当とみなされるべき資金移動を「借入金の返済」などと装うことで課税を回避しようとするケースも否認の対象となります。 これらの取引が否認されるかどうかは、経済的な合理性があるか、第三者でも同様の判断をするかどうかといった観点で判断されます。税務署長が否認の対象と判断すれば、課税関係は本来あるべき合理的な取引内容に基づいて修正され、結果的に追加課税や過少申告加算税などが生じることもあります。 「行為計算否認」という言葉は、税務や会計の専門家のあいだでは非常によく使われる用語であり、国税通達や裁判例にも頻出します。ただし一般的なニュースや日常会話ではあまりなじみがなく、「租税回避を否認する制度」といった表現に置き換えられることもあります。そのため、税務戦略を検討する場面では、こうした規定の存在を理解したうえで、実質に即した取引設計を行うことが求められます。
重加算税
重加算税とは、納税者が意図的に所得を隠したり、虚偽の申告をしたりするなど、特に悪質な税務違反を行った場合に、通常の税金や過少申告加算税などに加えて課される、ペナルティ的な性格を持つ税金です。たとえば、売上の一部を帳簿に記載しなかったり、架空の経費を計上したりといった行為があった場合に、税務署がその事実を確認すると、重加算税が課されることがあります。課税額は本来納めるべき税額に対して原則35%(場合によってはさらに高くなることもあります)が上乗せされるため、非常に重い負担になります。税制の公平性を保つとともに、不正な申告を抑止する役割を果たしており、税務調査などの際には特に注意が必要な制度です。