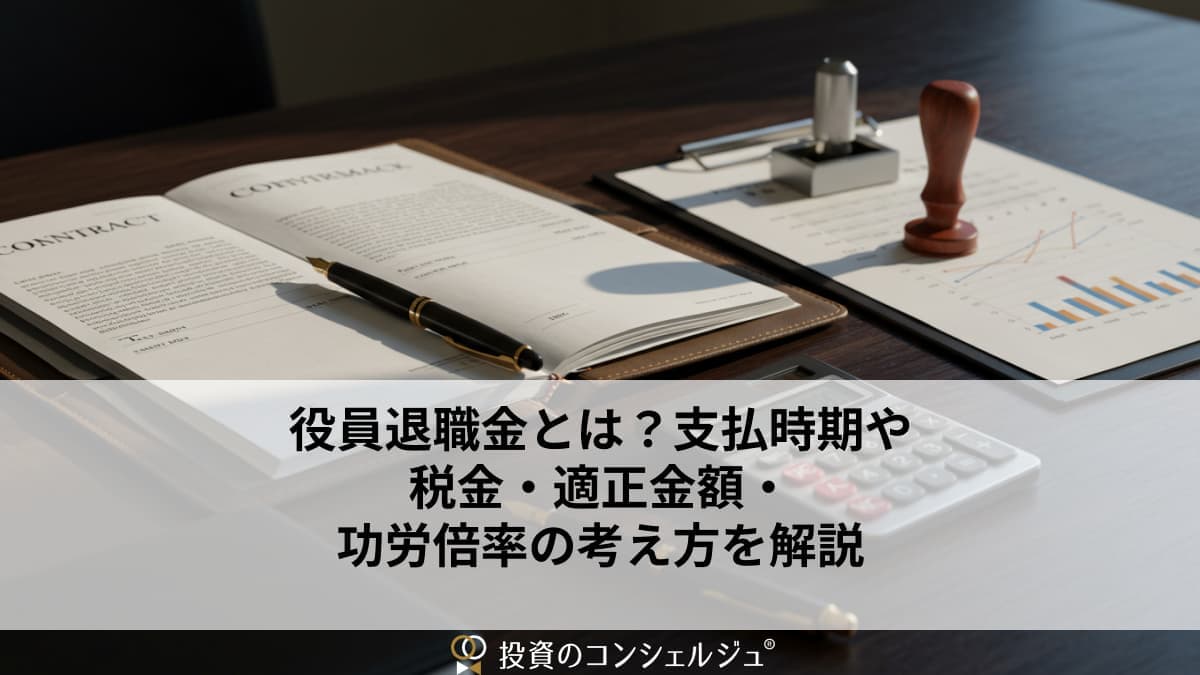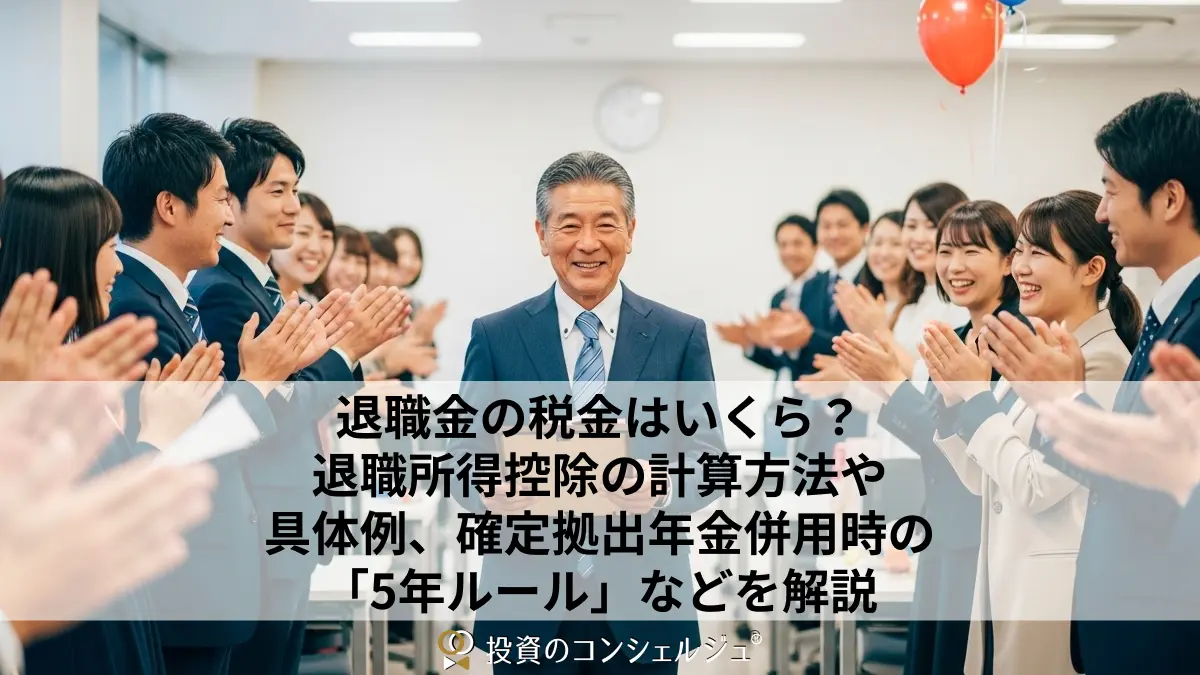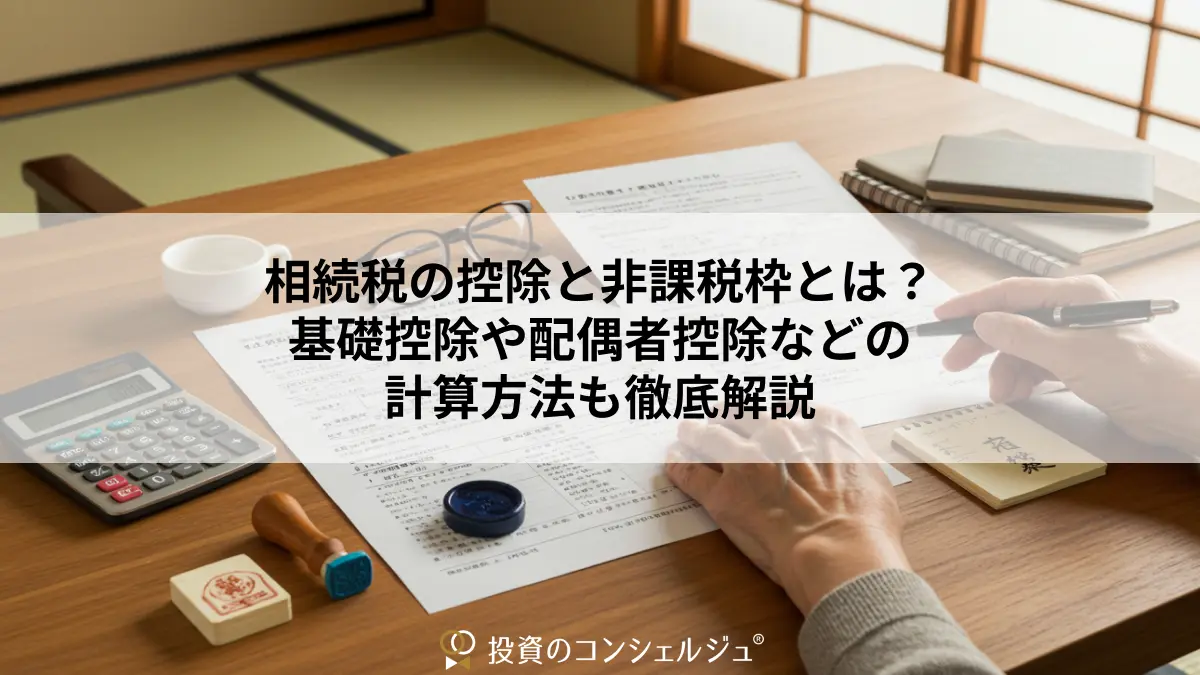特別功労金と退職金の違いは何でしょうか?また、一般的な支給水準や相場の考え方も教えてください。
特別功労金と退職金の違いは何でしょうか?また、一般的な支給水準や相場の考え方も教えてください。
回答受付中
0
2025/10/15 09:13
男性
60代
経営者や長年勤務してきた社員に対して、退職時に「特別功労金」や「退職金」が支給されると聞きますが、この2つはどう違うのかがよく分かりません。支給の目的や計算方法、税金の扱いなどにも違いがあると聞いたので、その点を詳しく知りたいです。また、役職や勤続年数によってどの程度の金額が一般的なのか、支給水準や相場の考え方も教えていただきたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
退職金は会社の規程に基づき、勤続年数や役職、退職理由などをもとに算出される退職時の一時金です。一方、特別功労金は通常の退職金に上乗せされる形で、会社への特別な貢献や功績に対して支給される特別な一時金を指します。どちらも退職に伴って支給される場合は、税法上は「退職手当等」として同じ退職所得の扱いになります。
税金の計算では、退職金・特別功労金ともに「退職所得控除」を差し引いたうえで、その残額の半分が課税対象となります。勤続年数が20年以下の場合は40万円×年数(最低80万円)、20年を超える場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)が控除額です。ただし、役員で勤続5年以下の退職金は特例の対象外で、半分課税の優遇が使えません。また、在職中に支給される功労金や賞与に近い性質のものは給与所得扱いとなり、退職金よりも税負担が重くなります。退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、源泉徴収時に控除や1/2課税が反映され、確定申告は不要になります。
一般的な支給水準としては、大企業では定年退職時に2,000万円台、中小企業では1,000万円前後が相場です。大学卒か高校卒か、勤続年数や職種によっても金額は変わります。退職理由が会社都合の場合は上乗せされ、自己都合だと少なめになるのが一般的です。また、企業年金を併用している企業では一時金が抑えられる傾向があります。
役員退職金や特別功労金の金額は、最終報酬月額に役員在任年数と功績倍率を掛ける「功績倍率法」で決められることが多いです。功績倍率は、社長で3倍前後、専務で2.4倍、取締役で1.8倍などが参考値とされます。特別功労金はこの退職金にさらに上乗せして支給されることも多く、金額は会社の判断によって個別に決められます。ただし、功労金が過大で合理的な根拠がないと、会社側で損金不算入となる可能性があるため、株主総会や取締役会の決議書などで支給理由を明確にしておくことが重要です。
死亡退職金や死亡功労金は相続税の対象となりますが、500万円×法定相続人の数までの非課税枠が適用されます。生命保険金の非課税枠とは別に扱われるため、遺族にとって有利な制度設計です。受け取り時は勤続年数の切り上げ計算を含め、控除を最大限活用することで税負担を軽減できます。
まとめると、退職金は規程に基づく基本的な支給、特別功労金は特別な貢献に対する上乗せ支給です。どちらも退職に伴い支払われる場合は退職所得として優遇税制の対象になります。相場は勤続年数や企業規模で異なりますが、大企業で2,000万円台、中小企業で1,000万円前後が目安です。適切な手続きと税務上の整理を行えば、税負担を抑えながら安心して受け取ることができます。
関連記事
関連する専門用語
特別功労金
特別功労金とは、企業や団体が長年にわたって勤務した従業員、または特に優れた業績を残した人物に対して、その功労をたたえて支給する一時金のことです。退職時や特定の成果を挙げた際に支給されることが多く、給与や賞与とは別に「功績への感謝」や「貢献への報奨」として位置づけられます。資産運用の観点では、この特別功労金を受け取った際に、将来の生活設計や老後資金の一部としてどのように活用するかが重要になります。特別功労金は一時的にまとまった金額となることが多いため、預貯金にとどめず、リスクを分散した投資や税制優遇制度を活用した運用を検討することで、より効果的に資産形成を進めることができます。
退職所得控除
退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。
給与所得
給与所得とは、会社などに勤めて働いたことによって得られる収入のことを指します。具体的には、月々の給料やボーナスなどがこれに該当します。会社員や公務員の方が受け取る報酬はすべてこの給与所得にあたります。税金の計算においては、収入金額から「給与所得控除」と呼ばれる必要経費のようなものを差し引いた後の金額が、実際の課税対象となります。投資の世界では、自分が得ている所得の種類を理解することが、資産運用の第一歩としてとても大切です。
功績倍率法
功績倍率法とは、役員退職金の金額を決める際に使われる代表的な計算方法のひとつです。この方法では、役員の最終報酬月額に在任年数をかけ、さらに「功績倍率」と呼ばれる係数をかけて退職金を算出します。 功績倍率は、その役員の会社への貢献度や役職の重要性、業績への影響などを考慮して決められます。たとえば、社長であれば高い倍率が設定されることが多く、在任期間が長ければ長いほど退職金も高くなる傾向があります。 税務上の適正額を判断する際にもこの方法がよく使われ、過大な支給とみなされると法人税の課税対象になる場合もあるため、適切な倍率の設定が重要です。資産運用や事業承継を考える際には、将来の退職金額を予測するうえで非常に役立つ考え方です。
損金不算入
損金不算入とは、法人が支出した費用であっても、税務上は経費(=損金)として認められず、課税所得の計算には含められない扱いのことをいいます。企業会計上では費用として処理されていても、法人税の計算においては損金として算入できないため、結果的に税金が多くなる要因になります。たとえば、役員に対する過大な退職金や交際費の一部、罰金・加算税などは、損金不算入となる代表的な例です。資産運用や経営判断の面では、損金不算入となる支出を誤って多く計上すると、予想以上の納税負担が生じてしまうため、税務の知識として正しく理解しておくことが重要です。
相続税
相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。